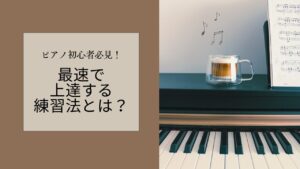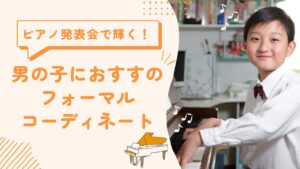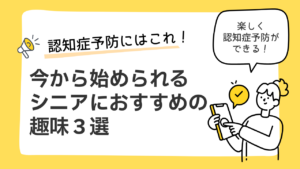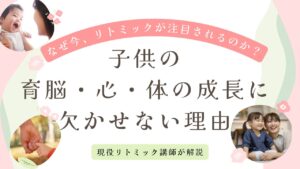「せっかくレッスンに通わせているのに、家ではぜんぜん練習しない…」「何度言ってもピアノに向かわないから、つい怒ってしまう…」そんなお悩みをお持ちの保護者様は少なくありません。実は、子どもが自らピアノに向かうようになるためには、ちょっとした親の関わり方が大きく影響します。柏市のハッピーミュージックでも、保護者の声を多く聞く中で見えてきた“うまくいく関わり方”をご紹介します。

うちの子、全然家でピアノの練習しないの・・・大丈夫?
「なんでやらないの?」より「どうしたらできる?」の視点に変える
「なんでまた練習してないの?」「もう何度言ったらわかるの?」お子さんにピアノの練習を促すとき、つい出てしまう言葉ではないでしょうか。保護者の皆さんが子どもの上達を願っているからこそ出てくる思い,それは本当に自然なことです。しかし、子どもにとってはこの言葉が「責められている」と感じられ、やる気をなくす原因になることもあります。
「なぜやらないの?」は子どもを追い詰めてしまう
「どうしてやらないの?」という質問は、大人の世界ではよく使われる合理的な問いかけです。しかし、子どもは「自分でもうまく説明できない感情」を抱えていることが多いため、理由を聞かれると戸惑い、責められているように感じてしまうことがあります。たとえば「疲れていた」「気分が乗らなかった」「他に気になることがあった」、そういった気持ちを、まだ言葉で表現できない子どもも多いのです。そんなときは、「じゃあどうすれば明日は少しでもできるかな?」と、未来に目を向ける声かけが効果的です。問い詰めるより、寄り添って一緒に考えることで、子どもは少しずつ自分の気持ちと向き合えるようになっていきます。


練習できなかった日より、「できたこと」を見つけてあげる
「全然やってないじゃない!」とつい言いたくなる日もあると思います。でも、1分だけ弾いた、指番号を思い出せた、楽譜を開いた、そんな小さな一歩を見つけて、「今日はそこまでできたね」と認めてあげることは、子どもにとって大きな励みになります。できなかったことより、できたことに目を向ける習慣が、子どもに「やってみようかな」と思わせる原動力になります。努力が報われる体験は、自己肯定感を高める最良の方法でもあります。
共感の言葉が、心のドアを開くきっかけに
やりたくない気分の日も、誰にでもあります。「今日はやる気出なかったのかな?」「疲れてる日もあるよね」と、気持ちに寄り添う一言は、子どもを安心させてくれます。「ちゃんとわかってくれてる」と感じることで、子どもは心を開き、少しずつ行動も前向きになっていきます。練習に向かわせることよりも、心の安心を与えることが、長い目で見て大切なサポートになります。
一緒に考える関係が、練習を“自分ごと”に変える
子どもが練習しないことにイライラしてしまうとき、視点を少し変えて、「この子はどうしたらできるのかな?」と考えてみてください。「明日は何時ごろなら弾けそう?」「ママも5分だけタイマーして応援しようか?」など、子ども自身が決められる選択肢を提示してみるのもおすすめです。子どもにとって、“自分で決めたこと”は特別な意味を持ちます。やらされる練習から、自分の意思で取り組む時間へ、その変化を生むのは、親子の対話と小さな成功体験の積み重ねです。
子どもが練習しないとき、つい「なんでできないの?」と責めるような気持ちになってしまうのは、親として自然な感情です。でも、視点を「どうしたらできるかな?」に変えるだけで、親子の関係はもっと柔らかく、あたたかいものになります。
“やらせる”より“やりたくなる”環境づくり
ピアノの練習を「どうやって続けさせよう…」と悩む保護者の方は多いと思います。
つい「練習しなさい!」と言ってしまい、そのたびに親子で気まずい雰囲気になることもあるのではないでしょうか。でも、子どもが自分から「弾きたい!」と思えるようになれば、そんなストレスも少しずつ減っていきます。今回は、練習を“やらせる”のではなく、“やりたくなる”ような環境づくりのコツをご紹介します。
ピアノを身近な存在にする工夫
ピアノがリビングの隅に置かれていて、普段の生活から遠い場所にある場合、子どもにとっては「特別なときにだけ触るもの」という印象になりがちです。できれば、家族の目が届くリビングの一角や、自然に足を運べる場所にピアノを置いてみましょう。また、譜面台に子どもの好きなキャラクターのシールを貼ったり、レッスンで使っている曲を録音して流しておいたりと、ピアノに触れる機会を自然に増やすことで、「なんとなく弾きたくなる」空気が生まれます。
練習のハードルをぐっと下げる
「1日30分」「曲を完璧に」など高すぎる目標は、子どもにとって大きなプレッシャーになります。まずは「5分だけ」「1回だけでもOK」など、ゆるやかなスタートを提案してみましょう。短い時間でも「今日もやったね」と認めてもらえることで、子どもは練習への抵抗感を減らし、自発的にピアノに向かうようになります。
「やらなきゃ」ではなく「これならできるかも」と感じられることが、やる気の第一歩です。
成長を“見える化”してモチベーションアップ
子どもは、自分の成長がわかるとやる気が続きやすくなります。
たとえば「練習カレンダー」を使って、できた日はシールを貼ったり、ポイントをためたりすると、楽しみながら継続できます。また、家族の前で小さな発表をする「おうちコンサート」も効果的です。拍手をもらう経験は、大きな自信とモチベーションにつながります。自分の努力が人に伝わる喜びを知ることで、「また弾きたい」という気持ちが育ちます。
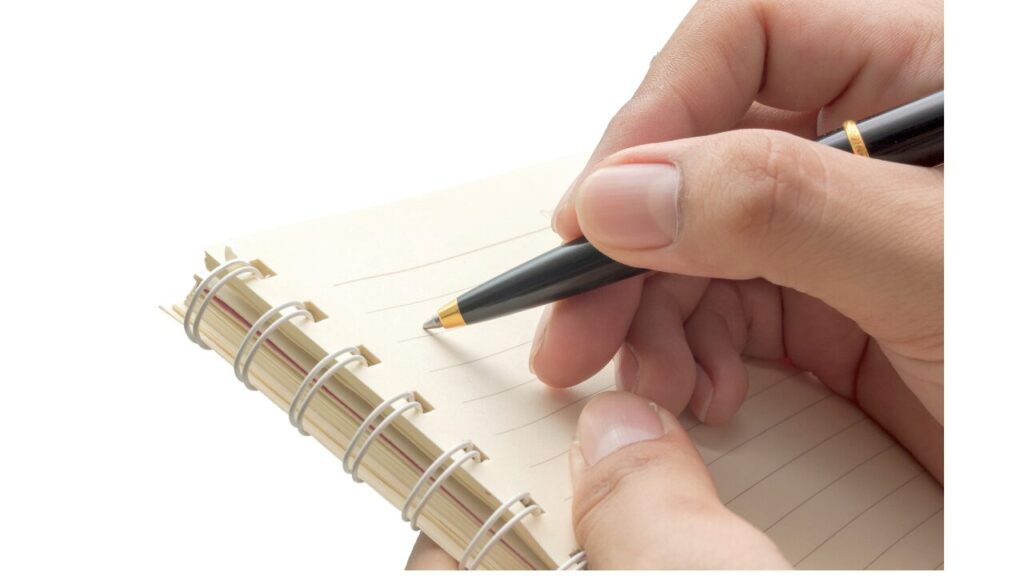
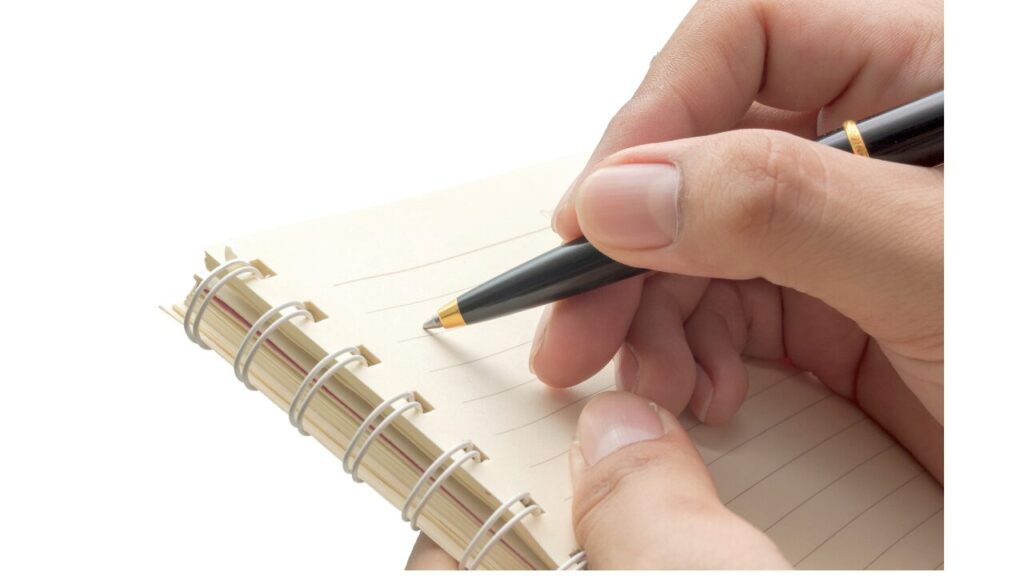
声かけは「評価」より「応援」を意識して
練習のあと、「まだ間違えてたね」や「そこ前も弾けなかったじゃない」など、つい口を出してしまうこともありますよね。でも、評価されすぎると、子どもは「また怒られるかも」と感じてピアノを避けるようになることも。それよりも、「いい音出てたね」「今日はピアノに向かっただけでえらいよ」といった、行動を認める声かけをしてみてください。うまくできたかどうかよりも、「見てくれている」「応援してくれている」と感じることが、やる気につながるのです。
子どもが自然とピアノに向かいたくなる環境は、ちょっとした工夫と温かな関わりで作ることができます。
毎日完璧に練習することよりも、音楽を楽しむ気持ちを大切にすることが、長く続ける秘訣です。
親のひと言がモチベーションのカギ!魔法の声かけ例
ピアノの練習が思うように進まないとき、つい強い言葉で注意してしまうこと、ありますよね。でも、子どものやる気は、実は親のたった一言で大きく変わることがあります。「言葉には力がある」とよく言われますが、それは子育てや習い事の場面でも同じです。今回は、日々の練習を前向きにする「魔法のような声かけ」について、ピアノ講師の視点からご紹介します。何気ない言葉が、お子さんの気持ちを動かすきっかけになるかもしれません。
「がんばったね」より「ちゃんと見てたよ」
「がんばったね」は素晴らしい言葉ですが、毎回同じだと少し曖昧に聞こえてしまうことも。それよりも、「今日は音がきれいだったね」「最後まで止まらずに弾けたね」など、具体的に見たことを言葉にすることで、子どもは「ちゃんと見てもらえてる」と実感できます。見てもらえている、理解されている――この安心感こそが、子どものモチベーションをぐっと高めてくれます。「また間違えた!」ではなく「そのチャレンジいいね!」ミスをしたときに「また間違えた」と言われると、子どもは自信をなくしてしまいがちです。でも、間違いは成長の証です。そんなときこそ、「挑戦してていいね」「難しいところ、頑張ってるね」と伝えてあげましょう。大人でも、努力を認めてもらえるとやる気が出るもの。失敗を否定せず、チャレンジする姿勢をほめることで、次も前向きに取り組めるようになります。
結果ではなく過程をほめる
つい「うまく弾けたね」と結果に注目してしまいがちですが、実は「毎日ピアノに向かってえらいね」「最初より指がよく動いてきたね」といった過程に注目した声かけの方が、長期的なやる気につながります。努力を認められると、「もっとやってみよう」と思えるようになります。成功だけを評価すると、「失敗したらダメ」と思い込むようになってしまうこともあるので、練習の姿勢そのものをほめる言葉を意識してみましょう。


子どもを“演奏者”として扱う言葉をかける
「今日の演奏、ママ好きだったな」「そのフレーズ、気持ちが伝わってきたよ」
このように、子どもを“ひとりの表現者”として尊重する声かけは、自己肯定感をぐっと育てます。音楽は、正解を当てるものではなく、心を込めて届けるもの。演奏を評価されるのではなく、感じたことを伝えてもらえると、子どもは音楽の本当の楽しさを知るようになります。
毎日の練習の中で、親がかけるひと言は、お子さんの心に深く残るものです。少し言い方を変えるだけで、子どもの表情がパッと明るくなったり、ピアノに向かう意欲が生まれたりする瞬間を、私たちはたくさん見てきました。
子どもの性格に合わせた関わり方のコツ
同じようにピアノを習っていても、練習への取り組み方やモチベーションの上がり方は、子どもによってまったく違います。「前は楽しそうに弾いてたのに…」「他の子はちゃんとやってるのに…」と悩む保護者の方も多いのではないでしょうか。でも実は、性格のタイプに合った関わり方をすることで、子どもは自分らしく音楽に向き合えるようになります。今回は、よく見られる4つの性格タイプを例に、効果的な関わり方のヒントをご紹介します。
マイペースタイプの子には「安心感」が鍵
自分のペースで動くのが好きで、あまり焦らされたくないタイプの子には、「早く!」「なんでやらないの?」という言葉は逆効果です。このタイプの子は、練習が遅れているわけではなく、納得してから動き出すのが特徴です。「今はちょっと休みたいのかな」「気持ちが整ってから始めるタイプだね」と、子どものリズムを尊重してあげると、自分から動き出す瞬間が増えてきます。スケジュールを決めるときも、「○時から練習しようか」と一緒に相談するスタイルがおすすめです。
完璧主義タイプの子には「失敗OK」の空気を
何でもきっちりこなしたい、間違えるのが苦手なタイプの子は、練習中にうまくいかないと自己嫌悪に陥りやすい傾向があります。このタイプは、他人に怒られるよりも、自分自身を責めてしまうことが多いのが特徴です。そんなときは、「失敗しても大丈夫」「間違えるって成長のチャンスだよ」と、繰り返し安心させてあげる声かけが大切です。うまくできたことよりも、努力している姿や、あきらめずに取り組む様子に注目してほめてあげると、心がほっとして、次のステップへ進みやすくなります。
頑張り屋タイプの子には「休むこと」も教える
いつも一生懸命で、言われなくても練習に取り組む子は、一見とても順調に見えますが、実はがんばりすぎてしまうことも。「ちゃんとしなきゃ」「先生や親にほめられたい」といった思いが強すぎると、無理を重ねてしまうことがあります。このタイプの子には、「今日はちょっと休もうか」「たまには好きな曲だけ弾いてみたら?」と声をかけて、気持ちの余裕を持たせてあげることが大切です。がんばる力は素晴らしい才能ですが、音楽を楽しむ気持ちを忘れないようにサポートしてあげましょう。


気分屋タイプの子には「選べる自由」を
その日の気分でやる気にムラがある子は、「ちゃんとやって!」と毎回同じように接しても響かないことが多いです。このタイプの子には、「今日はどの曲から弾きたい?」「タイマーする?しない?」など、ちょっとした“選択肢”を与える関わり方が効果的です。自分で選んだ、という感覚があると、不思議と行動に責任を持つようになり、「やらされてる」から「自分でやってる」へと変わっていきます。柔軟に対応することで、その子らしいリズムを大切にした関わりができます。
まとめ
「うちの子、まったく練習しなくて困っています」ピアノ教室でよく耳にするお悩みのひとつです。親としては、せっかくレッスンに通わせているのだから、ちゃんと練習してほしいという気持ちは当然ありますよね。けれど、子どもがピアノに向かうようになるきっかけは、「叱られたから」ではなく、「やってみたい」と感じたときにこそ芽生えるもの。そのために大切なのが、親のちょっとした声かけや、環境づくり、子どもの性格への理解です。
ピアノが「楽しい」に変わる環境を整える
子どもが自然とピアノに向かうためには、「やりなさい」と言うよりも、「やりたくなる」ような環境づくりが効果的です。リビングにピアノを置いて生活の一部にする、練習カレンダーを使って小さな達成感を味わう、家族の前で発表する機会をつくるなど、日常の中に音楽を取り入れる工夫をしてみましょう。「ピアノって楽しい」「今日も弾いてみたいな」と感じられる環境が、子ども自身のモチベーションを育ててくれます。
ひと言が変われば、やる気も変わる
「また間違えたの?」「もっとちゃんとやって」、つい口にしてしまう言葉が、子どもの心をしぼませてしまうこともあります。そんなときは、「今日もピアノに向かってえらいね」「その音、きれいだったよ」といった前向きな声かけに変えてみましょう。大切なのは、結果ではなく過程を見ること。努力したこと、挑戦したこと、気持ちを込めて演奏したことを、そっと認めてあげるだけで、子どもの目の輝きが変わってきます。


性格に合わせたサポートがカギ
子どもの性格によって、練習への向き合い方は大きく違います。マイペースな子には急がせず、完璧主義な子には失敗を恐れない安心感を。頑張り屋の子には休む大切さを伝え、気分屋の子には「選べる自由」を用意してあげることがポイントです。親が「うちの子はこういうタイプかも」と気づいてあげることが、ピアノとの距離をぐっと縮めるきっかけになります。一人ひとりに合った関わり方をすることで、子どもは自分らしいリズムで音楽を楽しむことができるようになります。
ピアノの練習を続けることは、ただ技術を身につけるだけではなく、心の成長や、自分と向き合う力を育む大切な時間です。そのサポート役である親の関わり方ひとつで、子どもの姿勢や気持ちは大きく変わります。叱るより、寄り添う。やらせるより、やりたくなる工夫を。子ども自身の力を信じて、小さな変化を一緒に喜べる関係を築いていけたら素敵ですね。