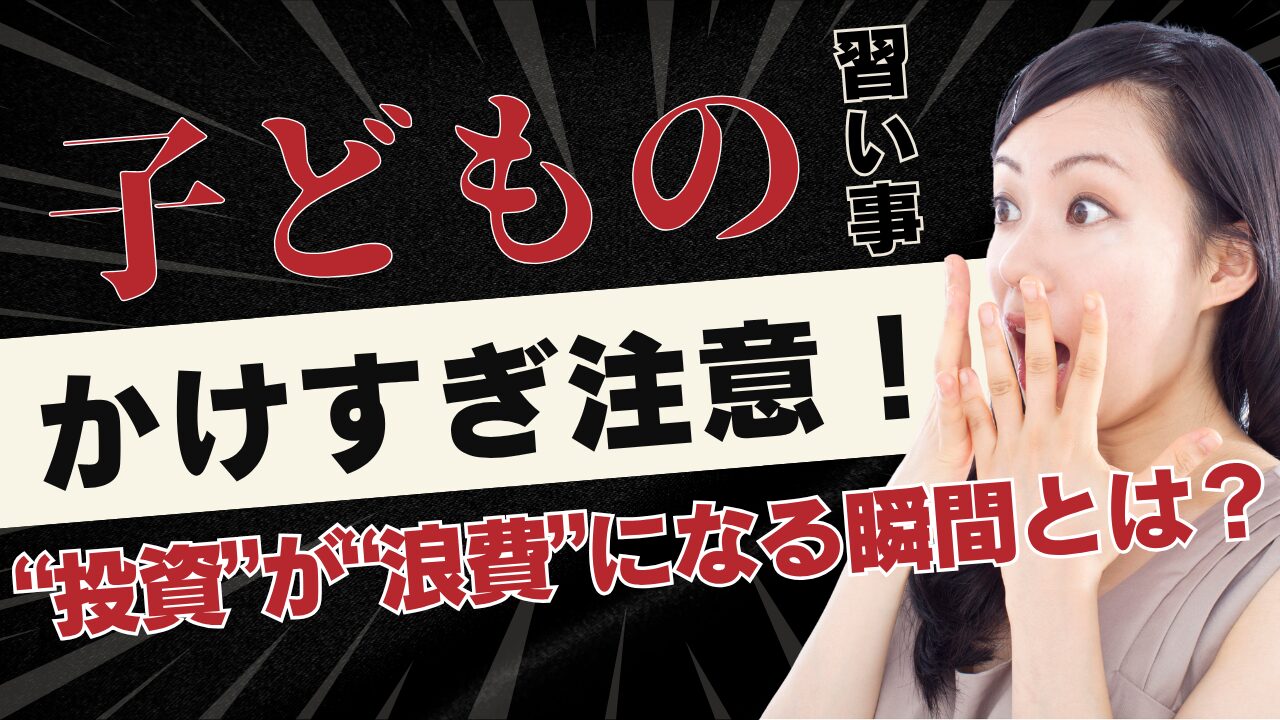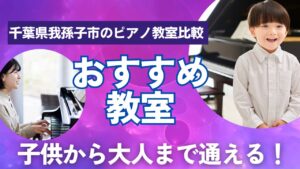「英会話にピアノ、水泳にプログラミング…。」子どもに少しでも多くの可能性を持たせたいと、親として習い事に力を入れるのは当たり前のこと。でも気づけば毎月の家計を圧迫するほどの出費に、「これって本当に必要?」と疑問を感じたことはありませんか?時には、親が目指す理想と子どもの本当の気持ちがズレていることも…。この記事では、習い事にお金をかけすぎた結果起こりがちなエピソードや、親として気を付けたいポイントを掘り下げてみます。さて、あなたの家庭の習い事事情は「投資」になっているでしょうか?それとも…?

習い事ってお金がかかるわ・・・
「やりたい!」と言ったのに3ヶ月で飽きる問題
子どもが「これ絶対やりたい!」と目を輝かせて言ってきたとき、親としては「この熱意を応援したい!」と思いますよね。新しい習い事に期待して道具をそろえたり、スケジュールを調整したりしてスタートするものの…気づけばわずか3ヶ月で「もう飽きた…」という衝撃の展開に。「えっ、あんなにやりたいって言ったのに!」とショックを受ける親も多いはず。そんな「3ヶ月で飽きる問題」には、意外な理由と面白さが隠れています。ここでは、この現象について詳しく掘り下げてみましょう!
子どもにとって「やりたい」は一瞬のキラメキ
子どもが「やりたい!」と言う時、それは瞬間的な好奇心や憧れから来ていることが多いです。例えば、友達が楽しそうに話しているのを聞いたり、テレビやSNSでカッコいい姿を見たりすると、「私もああなりたい!」と思うのです。でも、いざ始めてみると、実際にやることは地道な練習やルールの多い取り組みばかり。そのギャップに気づいて「思ってたのと違う…」と感じ、あっという間に興味を失ってしまうのです。この「一瞬のキラメキ」は子どもの成長の一環であり、失敗ではなく「好奇心の実験」なのかもしれません。
「努力より結果が欲しい!」という純粋な期待
子どもは物事を始めるとき、「自分もすぐに上手くなれる」と思っていることが多いです。ピアノを始めればすぐに大人顔負けの曲が弾ける、水泳を始めればあっという間に速く泳げる…そんな期待を抱いているのです。しかし現実は、指の動きがついていかなかったり、顔を水につけるだけで一苦労したりと、最初の壁が高く感じられます。その結果、「思ったより大変だな」と感じてしまい、やる気が急降下することに。子どもの「努力よりすぐ結果が欲しい」という純粋な気持ちは可愛いですが、親としては「最初は誰でもこんなもんだよ」と優しくサポートする必要があるでしょう。


興味が移り変わるスピードが超高速!
子どもの好奇心の移り変わりは、大人が想像するよりもはるかに速いものです。例えば、夏休みにプールで水泳にハマり、「水泳選手になりたい!」と言っていたのに、秋になるとテレビで見たサッカー選手に憧れて「やっぱりサッカーがいい!」と言い出すことも。これに親が振り回されると、「一体何が本気なの?」と困惑してしまうかもしれません。しかし、子どもにとっては興味が広がること自体が成長の証拠。色々なことに挑戦する中で「これだけは続けたい!」と思うものが見つかる瞬間がきっと来るのです。親はその過程を温かく見守るのが一番かもしれません。
「続ける」という経験がまだ未熟
子どもにとって「続ける」という概念は、大人が思うほど簡単なものではありません。新しいことを始める時にはワクワクしますが、日常的なルーティンや地道な練習を続ける中で「飽きる」という感覚が出てくるのは自然なことです。特に習い事は楽しさだけでなく、ある程度の忍耐力も必要になります。しかし子どもはまだ、その「忍耐力」や「習慣化」の経験が浅いため、どうしても途中で投げ出してしまうことが多いのです。でもこれは、習い事を通じて少しずつ学んでいくことの一環。むしろ「続けることの難しさ」を学ぶための第一歩だと思えば、飽きた経験も無駄ではありません。
子どもが「やりたい!」と言ったものの3ヶ月で飽きてしまうのは、実はとても自然なことです。それは子どもが好奇心を広げ、成長していく過程での一つの経験に過ぎません。大人の目線では「もったいない」と思えることも、子どもにとっては大切な学びの時間。親はその試行錯誤を温かく受け止めつつ、時には「もう少し続けてみたら?」と背中を押してあげることで、子どもの未来をより豊かにできるかもしれません。何より大切なのは、「やりたい!」という気持ちを尊重しながら、そのペースに寄り添うことです。
なぜか親がプロ級に詳しくなる現象
子どもの習い事を始めると、最初は「子どものために」と思ってサポートしていたはずが、なぜか気づけば親の方がその分野に詳しくなり、熱が入ってしまう…そんな現象を見たことがありませんか?例えば、子どもがピアノを習い始めたのに、親が楽譜を分析し始めたり、サッカー教室に通うはずが親が戦術を語りだしたり。本人そっちのけで「プロ級」にまで進化する親の姿は、時に面白く、時に滑稽で、そしてどこか愛おしいものです。ここでは、「なぜ親がプロ級に詳しくなるのか」を、4つのエピソードを通して探ってみましょう!
子どものためにリサーチを始めたら、止まらなくなる
最初は「子どもがスムーズに習い事を始められるように」と、ほんの軽い気持ちでリサーチを始めます。「ピアノの初心者にはどんな曲がいいのか?」「サッカーのポジションにはどんな役割があるのか?」と調べているうちに、情報がどんどん深掘りされていき、気づけば本や動画で学び始める親の姿が…。やがてその知識は、子どもの進度を追い越し、「お母さん、なんでそんなに詳しいの…?」と驚かれるレベルに。もはや「子どものサポート」の域を超え、自分が一番楽しんでいるのでは?と思わせる熱中ぶりは、家族を笑顔にしてしまうポイントです。


練習を見ているうちに“コーチモード”が発動する
子どもが習い事の練習をしているのを見ていると、つい親の「コーチ魂」が芽生えてしまいます。例えば、ピアノを弾く手つきが少しぎこちないと、「ここはこう動かすともっときれいに弾けるよ!」とアドバイスを始めたり、サッカーのキックが上手くいかないのを見て、「いや、もっとこう足をひねるんだ!」と実演し始めたり…。最初は子どものためと思っていたのに、いつの間にか「自分が教えた成果を見せたい」という気持ちが勝ってしまい、完全に“我が道を行くコーチ”になってしまうのです。その熱意に子どもは時に引き気味ですが、親が一緒に練習してくれること自体、子どもにとっては嬉しい思い出になるものです。
専門用語を駆使して周囲に語り始める
親がプロ級に詳しくなると、いつの間にかその分野の専門用語を使いこなすようになります。例えば、バレエを習っている子どもよりも親が「アラベスク」とか「ルルヴェ」といった言葉をさらりと使い、「このポーズが甘いわね」と評論家のようなコメントをする場面が増えたりします。さらに、その知識を他の保護者や親戚に語り出すことで、周囲は「え、〇〇ちゃんのお母さん、なんでそんなに詳しいの?」と驚きつつ苦笑い。子どもとしては「そんな専門的な話、まだ全然わかんないよ…」と肩をすくめるしかないのですが、親のこの「語りたくなる現象」も、愛情ゆえの行動といえるでしょう。
本人より親が夢中になる「趣味化」現象
子どもが習い事に使っている道具や技術に親がどんどん詳しくなり、最終的にはその習い事が「親の趣味」になってしまうことがあります。例えば、ピアノの習い事では「子ども用のキーボード」で十分だったのに、「もっと良い音の電子ピアノを買おう」とグレードアップを重ね、最終的には親が趣味で弾くための高級ピアノを購入してしまう…。また、スイミングの水着やゴーグル選びにこだわりすぎて、親がまるで競技選手のような装備を揃えてしまうことも。「子ども以上に夢中になってどうするの?」と家族からツッコまれつつ、楽しんでいる親を見ると、子どもも「お母さん、すごいな」と感心せざるを得ない場面もあるのです。
子どもの習い事は、親として支えたい気持ちがあるからこそ、つい熱が入りすぎてしまうもの。それが「プロ級に詳しくなる」という形で現れるのは、愛情の裏返しでもあります。ただし、あくまでも主役は子ども!親が先回りしすぎないように気を付けながら、時には一緒に楽しむ気持ちを大切にしていきたいですね。子どもが「ママ、なんかすごい!」と思う瞬間を増やしつつも、温かく見守るバランス感覚を忘れずに!
月謝や道具代に隠された「見えない出費」の罠
子どもの習い事を始めるとき、多くの親が「月謝や道具代ならこのくらいの出費で大丈夫」と考えて気軽にスタートします。しかし、習い事の世界には「見えない出費」という名の落とし穴が待ち受けています。初めて経験することばかりで気づかないうちに、発表会の費用や追加レッスン、さらには予期せぬグッズ購入で家計が圧迫されることも…。この記事では、習い事に潜む「見えない出費」の罠について、面白さを交えながら4つの事例をご紹介します。
発表会費用が“ミニ結婚式”並みに高い問題
特に音楽やダンス系の習い事では、「発表会」という一大イベントがあります。最初は「月謝さえ払えばOK!」と思っていた親も、突然の「発表会のお知らせ」に驚愕することに。衣装代、参加費、写真撮影代、さらには動画購入費など、気づけば「え、これって結婚式の準備かな?」と思うほどの出費が発生します。衣装は1回しか使わないのに数万円…なんてことも珍しくありません。さらに、発表会後には「打ち上げ会費」なるものまで追加され、親は財布とにらめっこしながら「こんなにお金がかかるなんて聞いてないよ…」と嘆く羽目に。それでも、子どもの晴れ舞台を見ると「ま、いっか」となってしまうのが親心なんですよね。
道具のアップグレードが止まらない現象
最初は「初心者用の道具で十分」と思って始めた習い事も、続けていくうちに「もっと良いものを揃えた方が上達するのでは?」と考え始めてしまうのが親心です。例えば、書道なら高級な筆や硯を買いそろえたり、スイミングなら新しい水着や高性能なゴーグルを何種類も揃えたり。さらにはピアノの場合、「この電子ピアノだと音が良くないから」とグランドピアノを検討し始める親も…。子ども本人はそこまで道具にこだわっていなくても、親が「どうせならいいものを」とエスカレートしてしまうのです。気づけば道具代が月謝の何倍にも膨れ上がり、「あれ、これって投資?それとも浪費?」と悩むことになります。


遠征や合宿で「旅行費用」並みの出費が発生
スポーツ系の習い事では、大会や合宿がつきものです。最初は「近場で練習するだけだろう」と思っていた親も、「今度の大会は隣の県で行われます」「合宿は〇〇県のリゾート施設で行います」という知らせに驚きます。交通費や宿泊費、さらに参加費まで重なると、もはや家族旅行並みの費用がかかることもあります。中には「応援する親御さんもぜひ一緒に!」という熱いお誘いがあり、結局家族全員での大移動になるケースも。遠征先でのご飯代やお土産代まで加わり、財布が軽くなりすぎて「なんでこんなに高くつくの?」と頭を抱えることに。さらに、兄弟姉妹がいる家庭では「下の子も一緒に行くから倍の出費!」というトラブルも発生します。
保護者コミュニティが生む「見えない出費の連鎖」
習い事を始めると、保護者同士の交流も増えますが、このコミュニティが意外な出費を生むことがあります。例えば、「みんなでお揃いのTシャツを作りましょう!」という案が出ると、断るわけにもいかずにデザイン代や購入費を負担することに。また、イベントの差し入れや、先生へのお礼としてのプレゼント代など、暗黙の了解で「みんなでお金を出し合う」場面が頻繁に発生します。最初は「ちょっとした金額だから」と思っていても、気づけば出費が積み重なり、「え、これもう月謝を超えてない?」と感じることも。親同士の付き合いも大切ですが、この見えない連鎖に巻き込まれるのは避けたいところです。
習い事にかかるお金は、月謝や道具代だけでは済まないことが多く、見えない出費が家計を圧迫する原因になることがあります。それでも、子どもが成長する姿や楽しそうに取り組む姿を見ると、「お金以上の価値がある」と感じるのが親心。大切なのは、事前にどんな出費があるかをしっかりリサーチし、無理のない範囲で楽しめる習い事ライフを送ることです。「見えない出費」も見越した計画を立て、親子で笑顔の絶えない時間を過ごしましょう。
子どもが忙しすぎて「ロボット生活」に突入
子どもにいろいろな経験をさせたい、可能性を広げてあげたい――そんな親心から、習い事を詰め込んでしまうことがあります。しかし、気づけばスケジュールがびっしり埋まり、学校、習い事、宿題のループで子どもの一日が終わるという事態に…。これでは、まるでプログラムされたロボットのような生活。子どもが「やりたい!」と思って始めたはずの習い事が、いつの間にか「やらなければいけないタスク」になってしまうのです。ここでは、子どもが忙しすぎて「ロボット生活」に突入してしまう様子を、4つの視点で面白く掘り下げてみましょう!
朝から晩までフルスケジュールで「子ども版ブラック企業化」
朝起きてすぐに学校へ行き、放課後は習い事の教室をハシゴし、家に帰ったら宿題をこなして寝るだけ…。まるでブラック企業で働くサラリーマンのようなスケジュールに追われる子どもたち。子どものカバンには学校の教科書だけでなく、ピアノの楽譜、水泳の水着、英会話のテキストが詰め込まれ、荷物の多さがまさに「働き盛り」のサラリーマン並み。本人も忙しさの中で無表情になり、「やるべきことをこなすだけ」の状態に突入します。親が「どう?楽しい?」と聞いても、「別に…」と機械的な返答が返ってくると、さすがに心配になってしまいますよね。
休みの日もスケジュール満載で「休む暇ゼロ」
平日の忙しさだけでなく、休日まで習い事や特別レッスン、試合や発表会で埋め尽くされる子どもたち。友達と遊ぶ時間もなく、家でのんびりすることもできず、気づけば「休む」という感覚を忘れてしまいます。日曜日の朝からサッカーの練習に行き、午後はピアノの補習、夜は英会話のオンラインレッスン…と、一日が終わるころにはクタクタに。週末が来ても「今週も頑張った!」という達成感を味わう暇もなく、次の予定が頭をよぎるのです。これでは、遊び盛りの時期にしか得られない大切な「自由な時間」が奪われてしまいます。
「疲れた」と口にできない子どもの本音
子どもは親の期待を感じ取るのが上手です。親が「これをやれば成長できる!」「これを続けてほしい!」と思っているのを敏感に察知して、「疲れた」と言いたいのに言えない子どもも少なくありません。学校から帰ると親が「次のレッスンの準備できた?」と声をかけてくるので、子どもは「嫌だ」とも言えず黙って出かける…。気づけば、「自分の気持ち」よりも「親が期待していること」を優先する生活になり、ますますロボット化してしまいます。そして、親が気づく頃には「もう全部辞めたい!」と泣き出すような事態になることも。子どもが本音を言える環境を作ることが大切ですね。
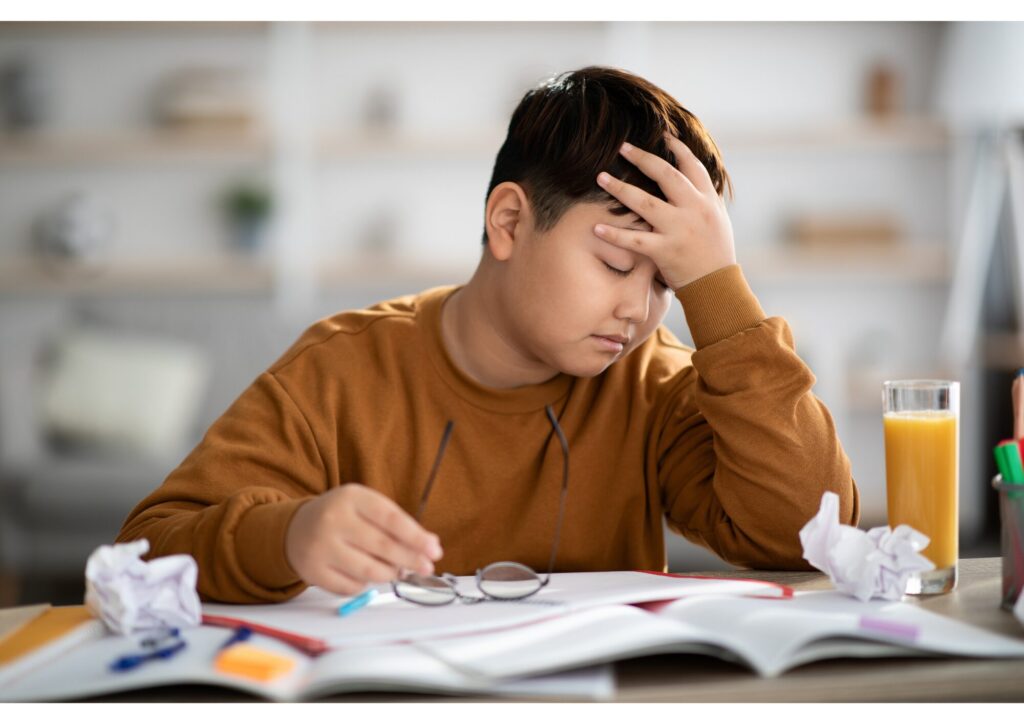
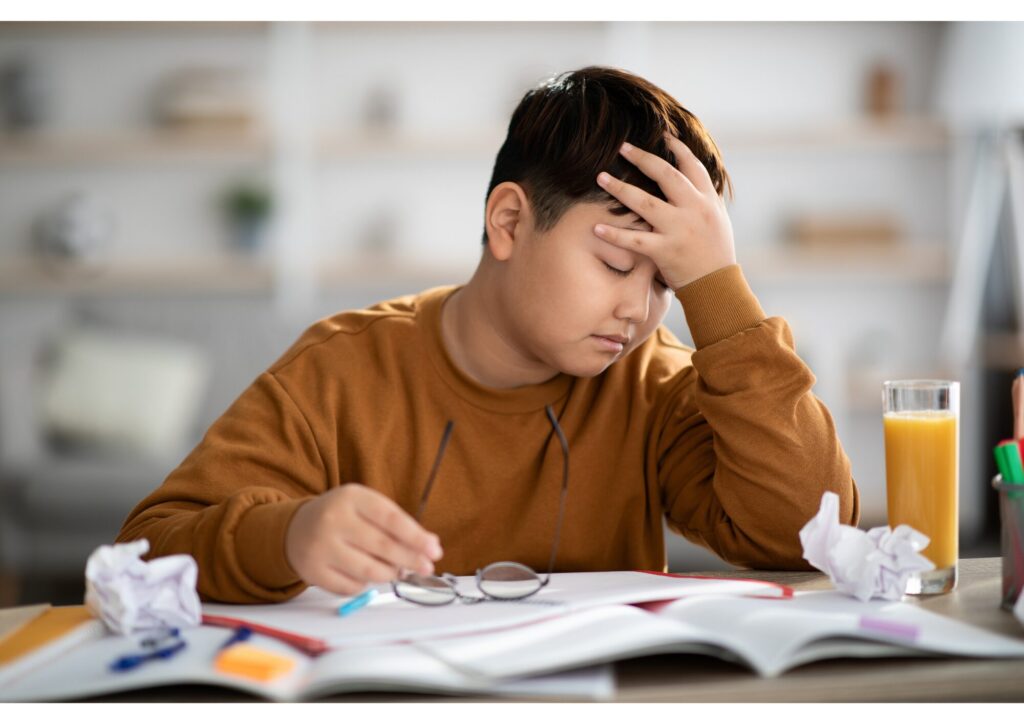
習い事が「目的」から「義務」に変わる瞬間
習い事は本来、楽しみや成長の場であるはずなのに、忙しすぎるスケジュールが続くと、それが「義務」に感じられるようになります。例えば、ピアノの練習が「楽しい!」から「次の発表会のために練習しなきゃ…」に変わったり、サッカーの練習が「仲間と遊ぶ場」から「監督に怒られないために頑張る場」になったりするのです。そんな中で、子どもの笑顔が消えてしまうのは辛い光景です。義務感で動くことが当たり前になると、「楽しい」という気持ちが薄れ、ただこなすだけのロボット状態に陥ってしまいます。これは親としても避けたい事態ですよね。
子どもが忙しすぎて「ロボット生活」に突入してしまうのは、親としては良かれと思ってのことが原因になることもあります。大切なのは、習い事やスケジュールを見直し、子どもが「自分の時間」を持てるようにすること。遊びや自由な時間も、子どもにとってはかけがえのない成長の一環です。「やらなければいけない」から「やりたい」に戻れるような環境を整え、親子で笑顔のある日々を過ごしていきましょう。
まとめ
子どもの習い事は、可能性を広げるための素晴らしい選択肢ですが、時にお金をかけすぎたり、子どもや親の負担になりすぎたりすることもあります。「やらせたい」という親の思いと、「やりたい」という子どもの気持ちのバランスを取ることが、より良い習い事ライフを送るための鍵となります。ここでは、習い事について親として考えたい重要なポイントを3つ挙げてみましょう。
習い事は量より質を重視する
多くの習い事を詰め込むよりも、子どもが本当にやりたいもの、楽しめるものを選ぶことが大切です。親が「やらせたい」と思うことと、子どもが「やりたい」と思うことを見極めることが重要です。
「見えない出費」や家計への負担を把握する
月謝だけでなく、発表会や追加料金、道具代など、習い事にかかる費用を事前にしっかりリサーチすることが、後から後悔しないための秘訣です。
子どもの成長や自由時間も大切にする
習い事でスケジュールを埋め尽くすのではなく、子どもが自由に遊んだり考えたりする時間を確保することで、心身ともに健康的な成長を促します。


習い事は「楽しい」「学びたい」という子どもの気持ちが一番の原動力です。無理なくバランスを取りながら、親子で笑顔の絶えない習い事ライフを楽しんでいきましょう。