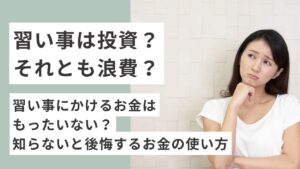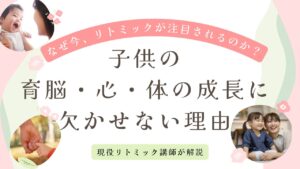「ピアノを始めたら、毎日何時間も練習しないとダメですか?」
保護者の方からよくいただく質問です。柏市のピアノ・リトミック教室 HappyMusic では、練習時間の長さよりも「どんな気持ちで練習するか」を大切にしています。子どもにとって初めてのピアノは、新しい世界への入り口。無理をしてしまうと「楽しい」よりも「つらい」が先に来てしまい、せっかくのやる気を失ってしまいます。では実際に、初めてピアノを習い始めた子どもには、どのくらいの練習が理想的なのでしょうか?今回は、HappyMusicらしい視点で「リアルな練習の目安」と「楽しく続ける工夫」をお伝えします。

練習ってなんだか気が重いわ・・・
最初は「1日5分」からで大丈夫
ピアノを始めたばかりのお子さんに「毎日30分練習しなさい」と言っても、なかなか続けられるものではありません。大人でも初めてのことをいきなり長時間取り組むのは大変ですよね。柏市のピアノ・リトミック教室HappyMusicでは、最初の練習は「1日5分」で十分と考えています。大切なのは時間の長さではなく、「ピアノに触れることを楽しいと感じられるかどうか」。ほんの少しでも弾けた達成感や、音を出せた喜びを重ねることで、子どものやる気は自然と伸びていくのです。
小さな習慣が大きな力に
「今日はピアノ触らなくてもいいか」と思う日が続くと、せっかくの学びが途切れてしまいます。そこでHappyMusicでは、まず「1日5分でいいから触ってみよう」という小さな目標から始めます。短い時間でも毎日続けることで「ピアノは毎日やるもの」という習慣が身につきます。習慣は力となり、自然に「もっとやってみたい」という気持ちに変わっていきます。最初から長時間を求めず、小さな一歩を積み重ねることが大切なのです。
短いからこそ集中できる
子どもは長い時間じっと練習するのが難しいもの。でも「5分だけ」と決めると、逆に集中できる場合が多いのです。また時間よりも小さなお子様には「回数」の方がわかりやすいかもしれません。「今日は3回弾いてみよう!」「今日はこのフレーズだけ」「右手だけをやってみよう」と小さく区切ることで、効率よく練習が進みます。そして「やった!できた!」という達成感が得られれば、子どもは次も自然にピアノに向かうようになります。練習は量ではなく質。5分に込められる集中が、成長の大きなエンジンになります。
遊びの延長で楽しく
子どもにとって練習は「やらされるもの」ではなく「遊びの延長」であることが理想です。HappyMusicでは「どの音が一番大きな音?」「今日はピアノでおばけの声を出してみよう!」など、子どもが夢中になれる工夫を取り入れています。5分間の中でも、遊び感覚で音に親しめると、子どもは「もっとやりたい!」と感じます。音楽の入り口にいる子どもにとっては、遊びのように自然と続けられる仕掛けこそが、やる気を育てる鍵なのです。


家庭での声かけが支えに
練習の習慣をつけるためには、家庭での声かけも大切です。「もっと練習しなさい」ではなく「今日の音、とてもきれいだったね」と認める言葉がけをすることで、子どもは「またやりたい」と感じます。HappyMusicでは、保護者の方に「どんな風に声をかけると子どもがやる気になるか」もアドバイスしています。家庭と教室が同じ方向を向いて応援すると、子どものやる気は定着しやすくなります。
ピアノを始めるときに大切なのは、長い時間を義務的に練習することではなく、「弾きたい」「やってみたい」という気持ちを育てることです。HappyMusicでは、1日5分からでも大丈夫という考え方を大切にし、子どもが自然と音楽を好きになれる環境づくりを心がけています。
練習=「復習」ではなく「遊びの延長」に
ピアノを習い始めると「宿題を復習しなきゃ」「毎日課題をやらなきゃ」と考えがちですが、それが子どもにとって「つまらない」「やらされている」という気持ちを生んでしまうことがあります。柏市のピアノ・リトミック教室HappyMusicでは、練習を単なる復習ではなく「遊びの延長」として楽しめるように工夫しています。練習が楽しいものになれば、子どもは自然とピアノに触れ、やる気を自分から伸ばしていくことができるのです。
音遊びから始めて「楽しい」を引き出す
「ドはどんな声?」「ピアノで雨の音を作れるかな?」といった音遊びは、練習を始めるときの導入にぴったりです。復習をいきなり真剣に取り組むのではなく、まず「音で遊ぶ」ことで子どもの気持ちがやわらぎ、自然に鍵盤に向かうことができます。遊びの中から「もっと弾きたい」という気持ちが育ち、練習のハードルも低くなります。
自分で考える余白をつくる
「今日はどの手から弾いてみたい?」「この曲を早くしてみる?それともゆっくり?」と問いかけると、子どもは自分の選択にわくわくします。HappyMusicでは、子どもが練習方法を自分で少し工夫できるような関わりを大切にしています。練習が「先生や大人に言われたことをやる時間」から「自分が考えて楽しむ時間」に変わることで、子どもは主体的に取り組むようになります。


成功体験を「遊び」で積み重ねる
例えば、同じフレーズを3回正しく弾けたら「今日のミッション成功!」とゲーム感覚で達成感を味わえるようにします。遊びの仕掛けを入れることで、ただの繰り返し練習が楽しいチャレンジに変わります。こうした小さな達成が積み重なると、子どもは自然に練習を続けられるようになります。
家庭での関わりも「遊び」目線で
保護者の方も「間違えたよ!」と指摘するのではなく、「その音、猫の声みたいだね」「今のフレーズ、かっこよかったよ!」といった楽しい声かけを意識するだけで、家庭での練習時間が明るくなります。教室と家庭が同じ目線で「遊びのように楽しむ」ことを大切にすると、練習は義務ではなく喜びに変わります。
練習を「やらなきゃいけない復習」として考えるのではなく、「音で遊ぶ時間」として取り組むことで、子どもは自然とピアノを好きになり、やる気が自分から育っていきます。HappyMusicでは、子どものペースと個性に合わせて、遊びの中に学びを散りばめたレッスンを大切にしています。
家庭での声かけがやる気を後押しする
ピアノを習い始めた子どもが「またやりたい!」と思えるかどうかは、教室だけでなく家庭での声かけにも大きく影響します。練習そのものは数分でも、その後に大人からどんな言葉をかけられるかによって、子どもの気持ちは大きく変わります。柏市のピアノ・リトミック教室HappyMusicでは、保護者の方に「どう声をかけると子どもがやる気になるか」を伝えることも大切にしています。正しいテクニックや指導法を教えるのは先生の役割ですが、家庭での温かい言葉がけが子どものやる気を定着させる一番の力になるのです。
褒めるときは「結果」より「過程」を
「上手に弾けたね」と結果だけを褒めるより、「昨日よりスムーズにできたね」「一生懸命がんばったね」と努力や工夫を認める言葉の方が、子どもは自分の成長を実感できます。HappyMusicでは、保護者の方に過程を見つけて褒める習慣をおすすめしています。そうすることで「次もがんばろう」という前向きな気持ちにつながります。


否定よりも受け止める
「間違えてばかりだね」「もっと練習しなさい」という言葉は、やる気をしぼませてしまいます。たとえ「やりたくない」と言われても、「そう感じたんだね」とまずは気持ちを受け止めることが大切です。そのうえで「じゃあ今日はここだけにしてみようか」と提案すれば、子どもは安心してもう一歩を踏み出せます。HappyMusicでも、子どもの気持ちを尊重する姿勢を大切にしています。
一緒に楽しむ姿勢を見せる
保護者の方が「ちょっと聞かせて」と興味を持ってくれるだけで、子どもは「聴いてもらえた!」と嬉しくなります。家庭で一緒に歌ったり、簡単なリズムを手拍子で合わせたりすることも大切な声かけのひとつです。練習が「一人で頑張る時間」ではなく「家族と共有できる時間」になると、やる気は一層高まります。
続けることを励ます
たとえ一度の練習が短くても、「今日もピアノに触れたね」と続けられたことを認めると、子どもは「毎日できている」という自信を持てます。HappyMusicでは、練習時間の長さではなく「続けること」に価値を見出す声かけを大切にしています。積み重ねを認める言葉は、子どものやる気を安定させる最大の後押しになります。
家庭での声かけは、子どもにとって「自分は認められている」という安心感を与え、やる気を育てる力になります。HappyMusicは、音楽の技術だけでなく、子どもの心を大切に育てる場でありたいと考えています。
練習の「量」より「質」を大切に
ピアノの上達と聞くと「毎日長い時間練習しなければならない」と思われがちですが、実は練習の効果を決めるのは時間の長さではありません。柏市のピアノ・リトミック教室HappyMusicでは、練習の「量」ではなく「質」を大切にしています。子どもは集中力が長く続かないもの。だからこそ、短い時間でも集中して取り組める練習こそが、やる気を損なわず、確実な上達につながるのです。
ダラダラよりもピンポイント練習を
ただ長く練習しても、間違えたまま繰り返したり、気持ちが散漫なまま続けたりすると逆効果になることがあります。HappyMusicでは「この部分だけを3回練習してみよう」「右手だけやってみよう」といったピンポイントの練習を大切にしています。小さな目標に絞ることで集中でき、成功体験も積み重ねやすくなります。
短時間でも毎日の継続が効果的
10分間しっかり集中する練習を毎日続ける方が、1時間を週に1回まとめてやるよりも効果的です。毎日触れることで、体がピアノの鍵盤を覚え、音楽の感覚も定着していきます。HappyMusicでは「1日少しでもピアノに触れる」ことを習慣化できるようにアドバイスしています。
練習方法を工夫して「楽しい質」を上げる
ただ同じことを繰り返すのではなく、リズムを変えて弾いてみたり、強弱をつけてみたりするだけで、練習は遊びのように楽しくなります。HappyMusicでは、子どもが自分で工夫して取り組めるように声かけをし、練習そのものがクリエイティブな時間になるようにしています。質を高める工夫が、練習の楽しさを広げます。


達成を感じられる仕組みを作る
「今日はここまでできた」「昨日よりスムーズに弾けた」といった成長を実感できると、子どもは次も頑張りたくなります。練習後に「ここまでできたね」と大人が一緒に確認してあげることも、質の高い練習を支える大切な要素です。HappyMusicでは、子どもと一緒に小さな達成を喜ぶことを重視しています。
練習は「長くやること」よりも「どんな気持ちで、どう取り組むか」が大切です。HappyMusicでは、短い時間でも集中して楽しく取り組める練習を通じて、子どものやる気と音楽の力を大切に育てています。
まとめ
ピアノを習い始めた子どもにとって、毎日の練習は上達のために欠かせません。でも「やらなきゃ」と思うだけでは、なかなか続かないのが現実です。柏市のピアノ・リトミック教室HappyMusicでは、子どもが無理なく楽しみながら練習を続けられるよう、やる気を育てる工夫を大切にしています。
練習は短くても毎日続けることが力になる
「最初は1日5分から」で大丈夫。大切なのは長い時間ではなく、毎日ピアノに触れる習慣をつけることです。短時間でも繰り返すことで音楽の感覚が自然と身につき、子どもは「できた!」という達成感を重ねることができます。


練習は復習ではなく遊びの延長にする
課題をただ繰り返すのではなく、「今日はどんな音が出るかな?」「このフレーズを早く弾いてみよう」と遊びのように取り組むことで、子どもは夢中になって練習します。楽しさの中に学びがあることが、やる気を引き出すポイントです。
家庭での声かけがやる気を支える
教室での学びが家庭で続くためには、保護者の声かけが欠かせません。「上手だったね」よりも「よく頑張ったね」「昨日よりスムーズだったね」と努力や成長を認める言葉をかけることで、子どもは自信を持ち、次の練習にも前向きに取り組むことができます。
ピアノ練習の目的は「長時間頑張ること」ではなく、「音楽を楽しみながら続けること」です。短くても集中する、遊び感覚で工夫する、家庭で温かく支える、この3つがそろうことで、子どものやる気は自然と定着していきます。HappyMusicでは、子どもたちが無理なく、楽しく、そして自分らしく音楽を続けられることを一番に考えています。