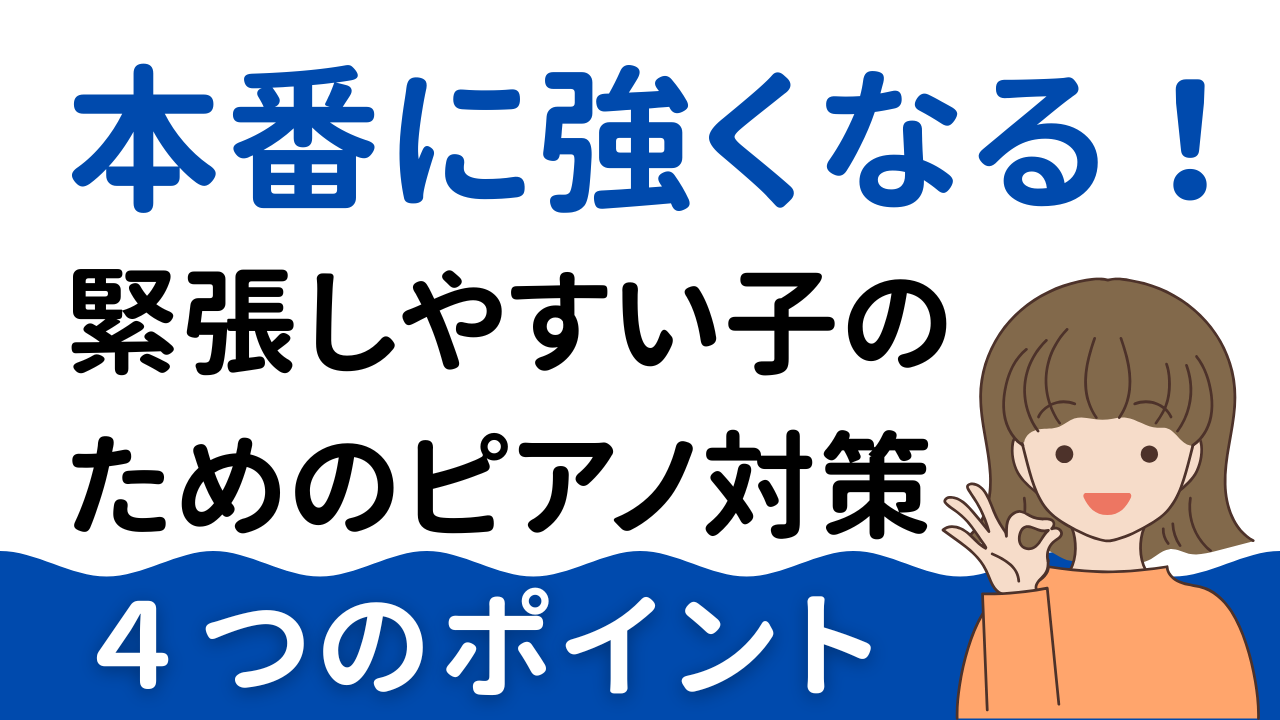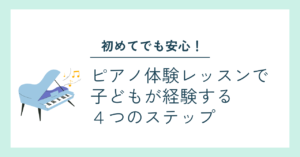発表会やコンクール、ちょっとした人前での演奏でも、子どもは思った以上に緊張してしまうものです。普段は弾けている曲なのに、舞台に立つと手が震えてしまう…。そんな経験をする子は少なくありません。けれども、緊張は決して悪いことではなく、適切なサポートや工夫で「力に変える」ことができます。ここでは、緊張しやすい子が安心して舞台に立ち、自分らしい演奏を楽しめるようになるための4つの対策をご紹介します。

うちの子、あがり症で心配だわ・・・
練習環境を「本番仕様」に近づける
ピアノの発表会やコンクールなど、本番の舞台で緊張してしまうのは自然なことです。普段はスラスラ弾けているのに、舞台に立つと手が震えたり音を間違えたり…。その多くは「本番特有の空気」に慣れていないことが原因です。だからこそ、普段の練習からできるだけ「本番に近い雰囲気」を再現することで、舞台での緊張を和らげ、自信を持って演奏できるようになります。
お辞儀から始める流れを習慣化する
本番の演奏は、椅子に座る前のお辞儀から始まります。練習のときも「登場 → お辞儀 →演奏 → お辞儀 →退場」という一連の流れを取り入れることで、舞台での動作が自然に身につきます。これを習慣化すると、本番でも動きに迷いがなくなり、自信を持ってステージに立てるようになります。
人前で弾く環境を少しずつ作る
本番に強くなるには「人に聴かれる経験」を積み重ねることが効果的です。家族や友達を前に座らせて演奏したり、スマホで録画して「誰かに見られている感覚」を体験したりするだけでも違います。特に録画は自分の姿勢や演奏を客観的に確認できるため、練習と本番のギャップを埋める良い手段になります。


服装や靴を本番用にして練習する
当日は普段と違う服装や靴で演奏することが多いので、慣れていないと違和感や弾きにくさを感じることがあります。発表会の直前には本番用の服や靴を実際に身につけて練習してみると安心です。「この格好で弾く感覚」を前もって体験しておくことで、当日の違和感を減らすことができます。
会場の雰囲気をイメージトレーニングする
実際のホールでのリハーサルができれば理想ですが、難しい場合もあります。そのときは「大きな舞台に立っている自分」「たくさんのお客さんが見ている中で弾いている自分」を想像しながら練習するのがおすすめです。イメージトレーニングは脳に「経験」として記憶され、本番での緊張を和らげる効果があります。
練習環境をできる限り「本番仕様」に近づけることは、緊張しやすい子にとって大きな安心材料になります。お辞儀や立ち振る舞いを含めた流れの練習、人前で弾く経験、本番に近い服装での練習、そしてイメージトレーニング――こうした準備を積み重ねることで、子どもは舞台に立つことを特別な出来事ではなく「いつもの延長」と感じられるようになります。緊張を和らげ、自信を持って演奏できるようになる一番の近道は、日常の練習から本番を意識することなのです。
小さな成功体験を積み重ねる
緊張しやすい子どもにとって、人前での演奏はとても大きな挑戦です。「失敗したらどうしよう」という不安が強く、普段の力を発揮できないこともあります。そんな子に必要なのは「自分はできる」という自信。その自信は、一度の大きな成功ではなく、日々の中で積み重ねてきた「小さな成功体験」から生まれます。小さな達成感を繰り返し味わうことで、子どもは自然と自信を深め、本番の舞台でも前向きに挑戦できるようになるのです。
短いフレーズを仕上げる喜び
いきなり一曲を完璧に仕上げるのは難しいですが、「今日は最初の4小節だけをきれいに弾けたね」と区切ることで、子どもは達成感を味わえます。部分的な成功を重ねていくと、やがて曲全体を完成させる力につながります。「少しずつできるようになっている」という実感こそが、緊張に負けない自信の源です。
人前での小さな発表を繰り返す
いきなり大きな舞台に立つのではなく、家庭内や友達の前で「ちょっと聴いて!」と演奏するだけでも大きな経験になります。家族から「上手だったよ」と認められることで、子どもは「人に聴かれるって楽しいんだ」と感じられます。小さな発表会を繰り返すことで、人前で弾くことに慣れ、本番での緊張を和らげられるようになります。


録音や録画で「自分の成長」を確認する
演奏を録音・録画して聴き比べることも、小さな成功を実感する方法のひとつです。子ども自身が「前よりスムーズになった」「音がきれいに響いた」と気づけると、大きな自信になります。さらに、録画を見せながら「ここが前より良くなったね」と具体的に褒めることで、努力が成果に結びついていることを実感できます。
成功体験を「見える化」する工夫
子どもは目に見える形で達成を実感できると、モチベーションが高まります。練習表にシールを貼る、できた曲を「できたリスト」に書き出すなど、小さな成功を積み上げていく仕組みを作るのがおすすめです。シールが並んでいくのを見て「これだけ頑張ったんだ」と確認できると、達成感が強まり、次の挑戦への意欲も高まります。
小さな成功体験は、緊張しやすい子どもにとって「安心の積み木」のような存在です。部分的な達成、人前での小さな発表、録音による成長の確認、そして成功を「見える化」する工夫――これらを積み重ねることで、子どもは「自分はできる」という確かな自信を育てていきます。その自信が、本番での緊張を和らげ、力を発揮するための最大の支えになるのです。
緊張を受け入れる声かけをする
「緊張しないでね」とつい言ってしまうこと、ありませんか?でも実は、この言葉は逆効果になることが多いのです。子どもは「緊張してはいけない」と思えば思うほど、余計にドキドキしてしまいます。大切なのは「緊張を否定する」のではなく、「緊張しても大丈夫」と受け入れてあげること。親や先生の言葉ひとつで、子どもの気持ちはぐっと楽になり、緊張を前向きな力に変えることができるのです。
「緊張してもいいんだよ」と伝える
子どもにとって「緊張すること=失敗につながる」という思い込みは強いものです。そこで「緊張するのは自然なことだよ」「上手に弾きたいと思っているから緊張するんだよ」と伝えると、安心感が生まれます。緊張を「悪いこと」ではなく「大切な気持ち」として受け止められるようになります。


緊張は力になることを教える
実は、少しの緊張は集中力を高める働きがあります。「緊張してるからこそ、いい演奏ができるんだよ」と声をかけてあげると、子どもは「このドキドキも役に立つんだ」と思えるようになります。緊張を「敵」ではなく「味方」に変えていく意識づけが大切です。
緊張した時の対処法を一緒に練習する
緊張はゼロにはできませんが、和らげる方法はあります。例えば「深呼吸をする」「心の中で好きな言葉をつぶやく」など。日常の練習から一緒に実践しておくと、本番で「緊張してもこれをやれば大丈夫」と安心できます。子どもに「緊張したらどうする?」と事前に考えさせるのも効果的です。
本番後に「よく頑張ったね」と声をかける
本番を終えた後、演奏が上手くいったかどうかよりも「緊張したけど舞台に立った」という行動そのものを認めることが大切です。「ドキドキしても最後までやり切れたね」「頑張った気持ちが伝わったよ」と褒めることで、子どもは「緊張しても大丈夫だった」という成功体験を積み重ねられます。
子どもにとって「緊張」は避けられないものです。けれども、大人の声かけ次第でその緊張は不安にもなり、自信にもなります。「緊張してもいい」「緊張は力になる」「緊張した時の方法がある」「緊張しても頑張れた」と伝えることが、子どもにとって大きな安心になります。緊張を否定せず受け入れることが、本番で子どもの力を引き出す一番のサポートなのです。
自信につながる日々の練習を大切にする
緊張しやすい子にとって、本番で自信を持って演奏するために欠かせないのが「毎日の練習」です。練習は単なる反復作業ではなく、子どもにとって「できるようになった」という感覚を積み重ねていく大切なプロセスです。日々の努力が小さな自信となり、その自信が本番の緊張を和らげる力になるのです。
短い時間でも毎日触れることが大事
長時間の練習を一気にするよりも、5分でも10分でも「毎日ピアノに触れる」ことの方が効果的です。毎日繰り返すことで指や耳が自然に慣れ、少しずつできることが増えていきます。この「昨日より今日、今日より明日」という積み重ねが、自信を支える土台になります。
「できた」を感じられる練習を工夫する
ただ弾くだけではなく、「今日はここまで弾けるようになった」「この部分は間違えずに弾けた」と小さな目標を作ることが大切です。練習のたびに「できた!」と感じられると、子どもの表情は明るくなり、ピアノへの意欲も高まります。小さな成功の積み重ねが大きな安心感へと変わっていきます。
練習を「確認の場」として活用する
練習は新しいことを学ぶだけでなく、「自分はここまでできている」という確認の場にもなります。録音をして聴き返したり、家族に聴いてもらったりすることで、自分の成長を実感できます。客観的に「できるようになった自分」を知ることは、本番での自信につながります。


習慣が「自分ならできる」という強さを育てる
練習を習慣にすることで、子どもは「自分は続けられる人だ」という自己肯定感を育むことができます。この「自分にはできる」という意識は、演奏だけでなく日常のさまざまな挑戦にも役立ちます。本番を迎えるとき、「毎日頑張ってきたから大丈夫」という思いが緊張を力に変えてくれるのです。
日々の練習は単なる繰り返しではなく、子どもにとって自信を育む大切なプロセスです。短時間でも続けること、小さな目標を達成すること、自分の成長を確認すること、そして習慣として根付かせること――これらを通じて、子どもは「自分はできる」という強さを手に入れます。その強さこそが、本番で緊張を乗り越え、自分らしい演奏をするための最大の武器となるのです。
まとめ
緊張は決して「悪いもの」ではなく、むしろ子どもが真剣に取り組んでいる証です。ただし、適切なサポートがなければその緊張は不安に変わり、せっかくの努力が本番で発揮できなくなってしまいます。そこで大切なのは「緊張をなくそう」とするのではなく「緊張とうまく付き合えるように導くこと」です。
日常の練習から本番を意識する
お辞儀から始める流れの練習や、人前での小さな発表、録音・録画など、普段の環境を「本番仕様」に近づけることで、舞台に立つことを特別視せずに済みます。練習と本番のギャップを埋めることが、安心につながります。
成功体験を積み重ねて自信を育む
一度の大成功よりも、小さな「できた!」の積み重ねが大きな力になります。部分練習の達成、人前での発表、録音による成長の確認など、日常の中で自信を増やしていくことが、本番での安心感へ直結します。


緊張を受け入れて力に変える
「緊張してもいい」「緊張は力になる」という大人の言葉かけが、子どもの気持ちを大きく変えます。さらに深呼吸やイメージトレーニングなど具体的な対処法を伝えておくことで、子どもは緊張を前向きなエネルギーに変えることができます。
緊張しやすい子にとって大切なのは「緊張しないようにする」ことではなく、「緊張しても大丈夫」と思える準備と心構えを育てることです。日々の練習や小さな成功体験、安心できる声かけの積み重ねが、子どもの心を強くし、舞台を楽しむ力を育てます。緊張を敵にするのではなく、味方につける、それが子どもが音楽を一生楽しむための大きな一歩になるのです。