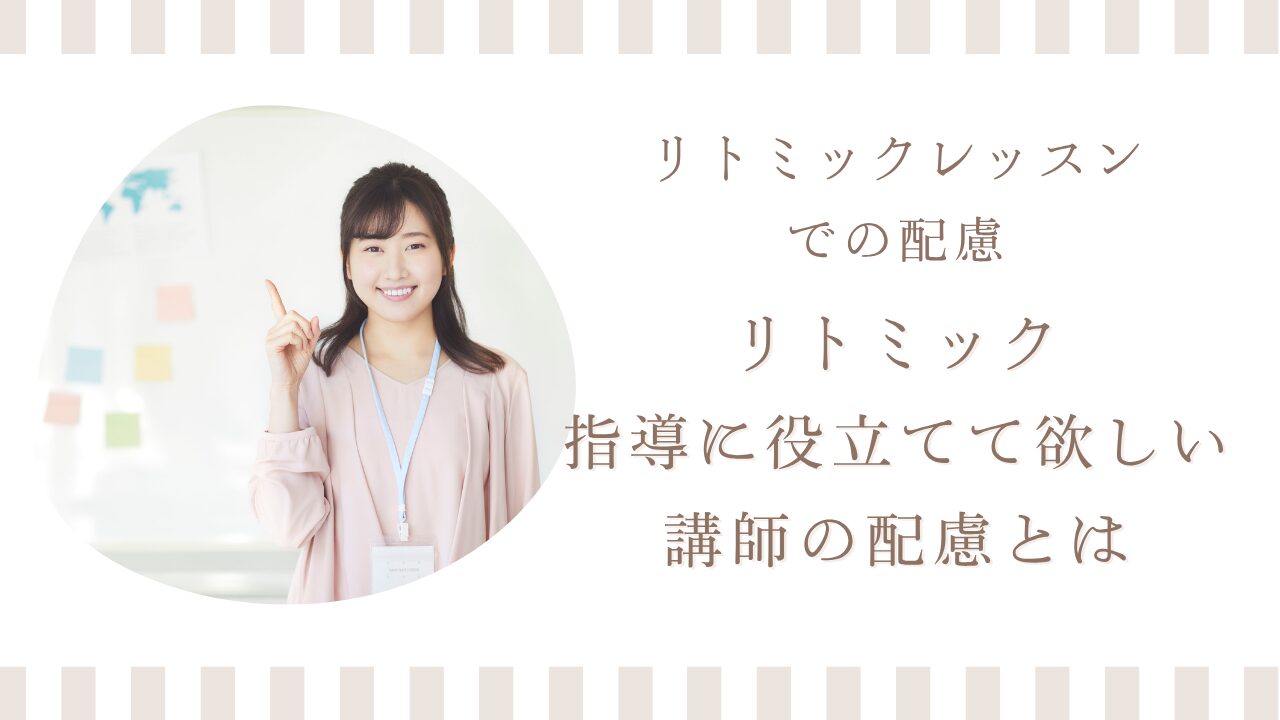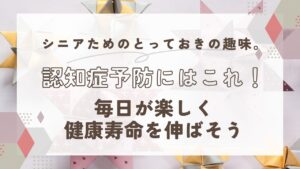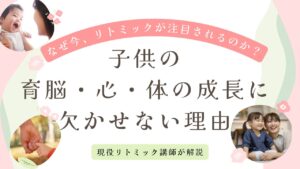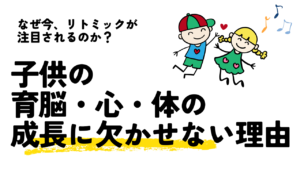リトミックレッスンしている講師はさまざまな配慮をしてレッスンを行なっていることと思います。しかし、時には具体的な配慮や、指導法が分からず悩んでしまうこともあると思います。リトミックとは、音楽に合わせて楽しく身体を動かし音楽を体で感じて深く理解する音楽教育法です。音楽を通して子どもの表現の幅を広げたり、感性や知性を育てたりする効果が期待でき、子どもたちが楽しめる要素が詰まっています。レッスンを充実したものにするためにも、今回はリトミックレッスンの配慮のポイントや指導ポイントなどについて詳しく解説します。
 平田先生
平田先生リトミック講師の私が詳しく解説します!
リトミックのねらい
リトミックはお遊戯やダンスと同じと思っている方がいますが、お遊戯やダンスは決められた動きを覚えて再現するのに対し、リトミックは、音楽を聴いて自分が感じたものを自由に身体で表現します。どちらも音楽に合わせて体を動かす活動ですが、お遊戯やダンスとリトミックでは目的の異なった活動であることが分かります。リトミックのねらいを説明します。
即時反応
言葉の通り、その場で考え反応する活動の事です。脳の「あっ!はっ!」体験です。音が止まると活動も止める、リトミックの課題に対し体で反応する、などの活動です。
ダイナミクス
よく使われるサブジェクトです。空間を使い体で音の大きさ、エネルギーを感じます。簡単なようですが、演奏に気をつけならなくてはなりません。また、最初はいいのですが「アリさんになろう!」などと声掛けをしてしまうとせっかくの子供の想像力が大人の指示によってなくなってしまうのできをつけましょう。演奏に対して「これは誰かな?」と答えを子供に導き出してもらうことが大切です。


ビート感、 拍子
音楽にはビートがあります。これは人間の心臓の鼓動と同じです。絶え間なく続くビート感を味わいながら、音楽を感じることが大切です。ビートを感じたら拍子を感じ、次第に違いを感じる課題に進歩します。
リズム・カノン
幼稚園、保育園の現場では手遊び歌をよく歌うと思います。その中にはリズム、カノンの課題が多く含まれています。その手遊び歌はよくできているな、と感心するものばかりです。課題としては、リズム打ち、マネっこ遊びすることで記憶して実行、カノンの要素が含まれます。例としては♪こぶたぬきねこ、♪やさいのうた、などです。どんどん歌遊びでリズム、カノンを使って体を動かして下さい。
長調、短調の聴き分け
音楽には、「明るい」「暗い」と言われる調性があり、その聴き分けの課題があります。長調、短調の演奏を聴きどんな気持ちかを表現します。また、リトミック中の演奏も楽しい場面、悲しい場面で演奏を工夫する必要があります。
リトミック活動で準備した方が良いもの
では、実際にどんな教具や準備をしたら良いかを紹介します。
わかりやすい絵
活動する内容がわかる絵を準備しましょう。子供達に見えるように大きめに作りましょう。動物園の絵、飛行機の絵、船の絵、海の絵、お弁当の絵など、活動に出てくる絵を準備し、視覚的に何をするか明確にしてあげましょう。
身近な楽器
鳴り物は子供の興味を誘います。タンバリン、すず、マラカス、太鼓など。お手製のマラカスを作り手に持って鳴らしても良いですね。リトミックは音楽教育ですから、楽器に触れることは大切なことです。


身近な小道具
音が鳴らなくても、音を感じる様々な身近な小道具はあります。例えば、ボール、スカーフ、フラフープ、ポンポン、紐、など。これらを音に合わせて振ったり回したりすることで音を感じられる動きを知ることができます。子供はまず目で見える事で認識が始まり興味を持ちます。色などに執着する行為もその1つです。教具はリトミックにおいて音を目で認識し、感じられる大切な役目があります。
教材は子供の指導に欠かせないアイテムなことがわかりました。工夫次第で身近なもので音楽を感じられる道具になります。
子供への配慮
リトミックレッスンを行う際、子供への配慮として重要なポイントをお話しします。
年齢や発達段階に応じた活動の設定
子供の年齢や発達段階に合わせて、無理のない課題や活動を設定することが大切です。たとえば、小さな子供には簡単なリズム遊びから始め、大きくなるにつれて複雑な動きや協調性を必要とする活動を増やしていきます。成長に応じた柔軟なプログラムを用意しましょう。
個々のペースを尊重する
子供たちはそれぞれのペースで学びます。指導中にすぐに結果を求めるのではなく、一人ひとりが楽しく参加できる雰囲気を作りましょう。苦手な動きを強制しないで、自然と興味を持つように促す工夫をします。
安心感の提供
初めての環境や音楽活動に緊張する子供も多いです。明るく優しい声かけを行い、失敗しても安心できる雰囲気を作ることが大切です。保護者が参加できる場合、最初は一緒に活動してもらうのも良い方法です。


集中力の配慮
子供の集中力には限界がありますので、1つの活動を短時間で切り替えることを意識します。動と静のバランスを取り、動きのある活動(ダンスやステップ)と静かな活動(座って聞く時間や手遊び)を組み合わせることで、飽きずに楽しめる工夫をします。
これらを意識することで、子供たちがリトミックを通じて音楽と体の動きに親しみ、自然な成長を促すことができます。
付き添う保護者への配慮
リトミックレッスンに子供を付き添う親への配慮として、以下の4つのポイントを意識すると良いです。
親子でリラックスできる雰囲気作り
親が緊張していると子供にも伝わります。明るい挨拶やフレンドリーな態度で、親もリラックスできる雰囲気を作りましょう。レッスンの最初に「どんなことを楽しむか」を簡単に説明しておくと安心感を与えられます。
親の関与の仕方を明確に伝える
親がどの程度レッスンに参加するべきかを具体的に説明します。例えば、子供が不安そうなときには近くで見守る、時には一緒に体を動かすなど、役割を分かりやすく伝えましょう。親が「どこまで手を出すべきか」を理解すると、子供に安心感を与えやすくなります。


親同士の交流機会を提供する
レッスンの合間に簡単な交流タイムを設けると、親同士がつながりを持てるようになります。これにより、孤立感が軽減され、親もリラックスして参加できます。無理のない範囲で「お話しの時間」や「質問コーナー」を設けるのもおすすめです。
負担にならない進行と配慮
親に過度な負担をかけないように、特別な準備や長時間の拘束は避けます。動きやすい服装で十分であることを伝えたり、気軽に参加できるスタイルを心がけましょう。また、親子での参加が難しい家庭(兄弟の世話がある場合など)への柔軟な対応も必要です。
親が安心してリトミックに参加できる環境を作ることで、子供たちもより楽しく成長できる時間を過ごせます。
まとめ
楽しい時間であることでリトミックの効果は高まると思っています。お話ししてきた配慮を忘れずにレッスンを進めてみて下さい。
リトミックレッスンでの配慮
リトミックレッスンでは、年齢や発達に合った内容を用意し、具体的に分かりやすいもの、視覚的に楽しいものであるとレッスンは効果的になります。レッスンでの動きや音楽を自然な形で分かりやすく指導することが重要です。


子供への配慮
子供のリトミックレッスンでは、年齢や発達に合った内容を用意し、一人ひとりのペースを尊重することが大切です。失敗しても安心できる雰囲気を作り、活動を短く区切って集中力を保ちます。また、子供が楽しみながら成長できるよう、動きや音楽を通じて自然な学びを促します。
保護者への配慮
リトミックに付き添う保護者には、リラックスできる雰囲気を提供し、レッスン中の関わり方を明確に伝えることが大切です。親が負担を感じないよう配慮し、他の保護者との交流の場を作るなど、安心して参加できる環境を整えます。
つい指導に力が入って、細かな配慮が足りないことが私にもあります。しかし、目の前の子供、付き添う親御さんの立場になった時、どんなことをしたら嬉しいか、分かりやすいか、楽しいかを考えると自ずと配慮は見えてきます。