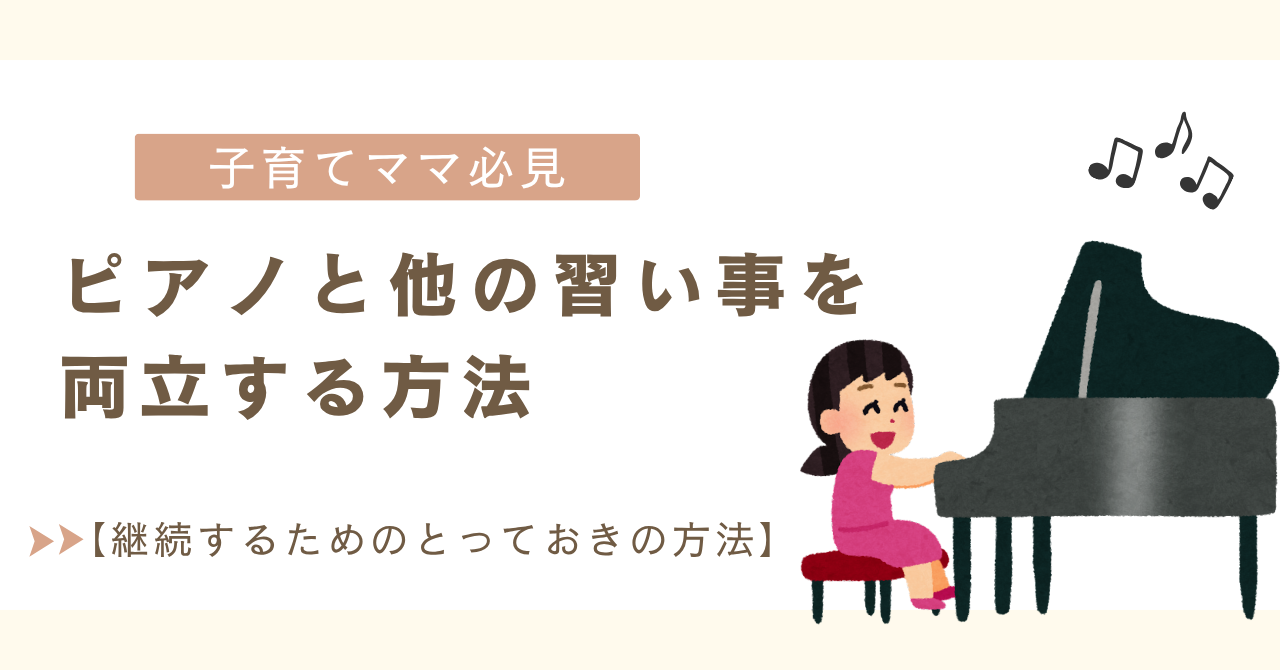「ピアノも続けたいけど、サッカーもやらせたいし、英語も…」子どもの将来を考えると、できるだけ多くの経験をさせてあげたいと思うのが親心です。ピアノは感性や集中力を育て、表現の幅を広げる習い事。一方で、スポーツや英会話、学習塾なども、子どもの成長に欠かせない要素を持っています。でも、1日は24時間しかありません。学校や家庭での時間、習い事の時間、休息の時間をどう配分するかは、どのご家庭でも頭を悩ませるテーマです。っ今回はそんなお悩みを現役講師の私が、無理なく両立を続けるための4つの視点と具体的な工夫をお伝えします。

習い事をいろいろさせているけど両立が難しくて
目的と優先順位を家族で共有する
ピアノと他の習い事を両立させるためには、まず「なぜそれを続けるのか」という目的を家族全員で共有することが欠かせません。目的や優先順位がはっきりしていれば、忙しいときや予定が重なったときにも迷わず判断でき、子どもも納得して取り組むことができます。
目的を言葉にしてみる
両立のスタート地点は「なぜその習い事をやるのか」をはっきりさせることです。
例えば、ピアノは「表現力と集中力を育てるため」、サッカーは「体力づくりと協調性を養うため」というように、理由を明確にします。
あるご家庭では、家族会議で全員が順番に目的を話し合い、その内容を紙に書いてリビングに貼っていました。試合や発表会が重なったとき、その紙を見て冷静に判断できたそうです。失敗例として、目的を共有していないと、本人が納得しないまま親が選んでしまい、「なんでこっちを休まなきゃいけないの?」と不満が募るケースがあります。
習い事同士の関係性を見つける
両立はただ時間を分け合うことではありません。習い事同士の相乗効果を見つけると、相互に刺激し合いながら成長できます。たとえば、ダンスで培ったリズム感はピアノ演奏のテンポ感を自然に良くし、ピアノで身につけた集中力はサッカーの試合中の冷静な判断につながります。英会話を習っている子が洋楽に興味を持ち、ピアノで弾き語りをするようになった例もあります。
家族で優先順位を決める
試合と発表会が同日に重なったとき、事前に話し合いができていないと当日大きな混乱が生じます。あるご家庭は「発表会は年に1回、試合は毎月あるから、今回は発表会を優先しよう」という基準を共有していました。そのため子どもも納得し、両方に前向きな姿勢を持ち続けられました。


定期的に見直す
一度決めた優先順位も、子どもの成長や生活リズムによって合わなくなることがあります。半年に一度や学期の切り替え時など、区切りのタイミングで「今何を大事にしたいか」を親子で話し合いましょう。ここで大事なのは、まず子どもの気持ちを聞き、その後に実際のスケジュールや疲れ具合などの状況を整理することです。話し合いの内容は簡単なメモとして残し、次回の見直しに活かします。こうした小さな調整を積み重ねることで、ピアノと他の習い事の両立は無理なく長く続けられます。
「目的と優先順位を家族で共有する」ことは、ピアノと他の習い事を無理なく両立させるための土台です。なぜその習い事を続けるのかという理由を家族全員で言葉にし、発表会や大会などのイベントが重なったときの判断基準として共有しておくと迷いが減ります。また、一度決めた優先順位も固定せず、子どもの成長や生活の変化に合わせて定期的に見直すことで、本人の納得感とやる気を保ちながら長く続けることができます。
時間のやりくりは「細切れ時間」と「ルーティン化」
「時間がないから練習できない」――そう感じてしまうご家庭は多いですが、実は日常の中に小さな“すき間時間”はたくさん隠れています。その短い時間を上手に使い、生活の流れに練習を組み込むことで、無理なく続けられる習慣が生まれます。これが、ピアノと他の習い事を両立させるための大きな鍵になります。
細切れ時間を宝物にする
「まとまった時間がないから練習できない」と考えると、練習ゼロの日が増えてしまいます。でも5分や10分の空き時間は意外とあります。
ある生徒は、朝起きて制服に着替える前に右手だけの練習をし、夕食前に音階練習、寝る前に好きな曲を弾く——これで一日合計20分。短時間でも毎日触れることで、指の感覚や曲の記憶が途切れません。
逆に「時間がないからやらない」日が続くと、発表会前に焦って詰め込み練習になり、演奏が不安定になりがちです。
「決まった順番」に組み込む
練習するかどうかを毎日考えると、その判断に時間とエネルギーを使ってしまいます。「おやつの前にピアノ」「歯磨きの前に音階」など、日常の流れに組み込むと、迷わず椅子に座れるようになります。ある家庭では、キッチンタイマーを使い、おやつの後に10分だけ弾く習慣をつけました。タイマーが鳴ると自然に練習モードになるため、声かけの必要も減ったそうです。
家族全員のスケジュールに合わせる
家族全員の生活リズムを揃えることは、子どもの練習習慣を安定させるためにとても効果的です。たとえば、兄弟がテレビを見ていたり、家の中が騒がしい時間に練習しようとすると、集中力が途切れやすくなります。逆に、家族みんなが静かに過ごしている時間を練習にあてれば、自然と落ち着いて取り組める環境が整います。あるご家庭では、夜8時から30分間を「集中タイム」と決めました。その間、兄弟は宿題、親は読書や家事を静かに行い、子どもはピアノに向かいます。このルールを作ったことで「練習しなさい」という声かけが不要になり、親子ともにストレスが減ったそうです。
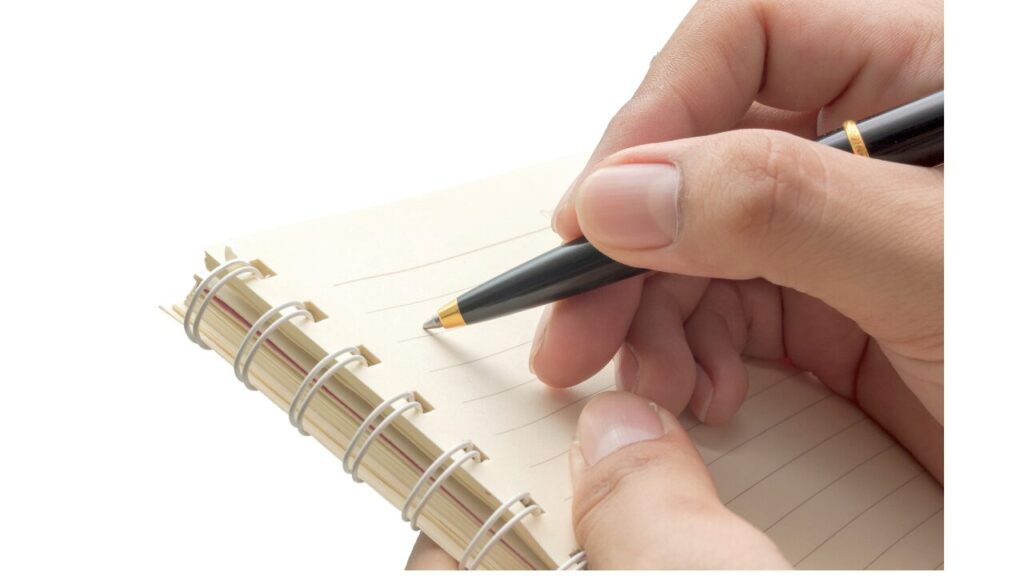
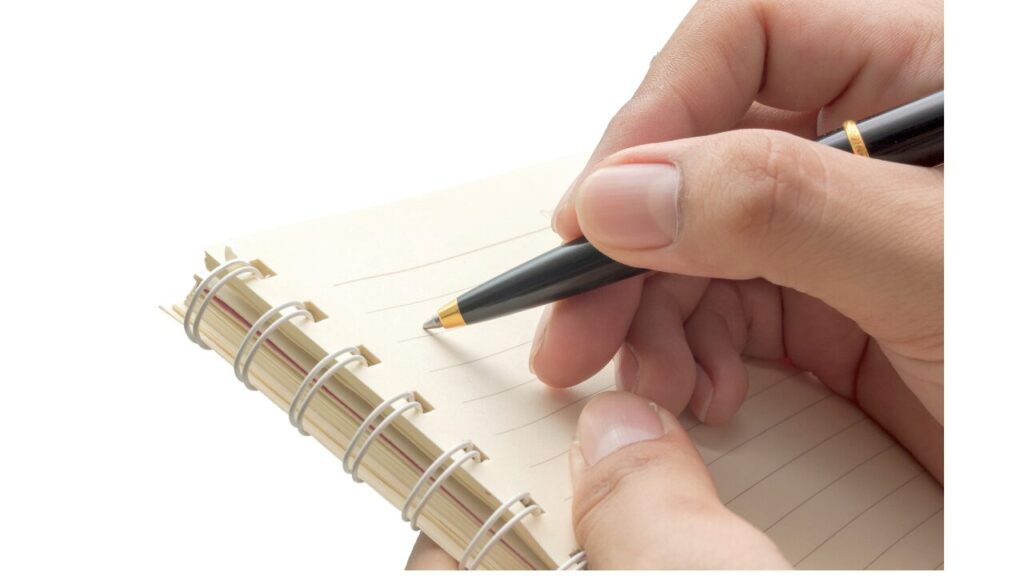
練習の質を上げる
短い時間でもしっかり成果を出すには、ただ通しで弾くのではなく、その日の目的をはっきり決めてから始めることが大切です。「今日は右手のメロディだけ」「この2小節のリズムを安定させる」など、範囲やテーマを絞ると集中力が高まり、短時間でも確実に上達できます。私の教室では、練習メニューを小さな付箋に1つずつ書き、終わったらO Kと書き込む方法をおすすめしています。目に見える形で「できた!」が増えていくと達成感が残り、子ども自身も「今日はここまでやろう」と意欲的に取り組むようになります。こうした工夫は、時間が限られているときほど効果を発揮します。
「細切れ時間」と「ルーティン化」を活用すれば、忙しい日常の中でも練習を習慣として根付かせることができます。5分や10分の短い時間でも、毎日触れることで感覚は途切れず、確実に上達につながります。また、生活の流れの中に練習時間を固定して組み込むことで、「やるかどうか」を迷う必要がなくなり、家族全員が協力しやすい環境が整います。限られた時間でも質を意識した練習を重ねることで、ピアノと他の習い事の両立はぐっと現実的になります。
モチベーションを高める仕掛けと周囲のサポート
ピアノと他の習い事を長く続けるためには、時間管理だけでなく「やる気を保つ工夫」が欠かせません。小さな達成感や周りからの応援が積み重なることで、子どもは自然とピアノに向かいたくなります。モチベーションを引き出す環境づくりこそが、両立成功の大きなポイントです。
成果を披露する場をつくる
人に聴いてもらう機会は、子どものやる気を一気に引き上げます。大きな発表会や教室のコンサートだけでなく、家族や親しい友人に向けた小さなお披露目でも十分です。たとえば、月末に祖父母の家で3曲だけ弾く、友達が遊びに来たときに1曲披露するなど、日常の中に発表の場を組み込むと、練習の目的が明確になり、集中力も増します。小さな拍手や「上手になったね」という一言が積み重なって、自信と継続する力につながっていきます。
他の習い事との相乗効果を見つける
他の習い事で身につけた力は、思いがけない形でピアノにも活きてきます。たとえば、バレエで培った姿勢や体幹の安定は演奏中のフォームを美しく保ち、サッカーで鍛えた集中力や瞬発力は、難しい曲のリズム感やテンポの切り替えに役立ちます。こうしたつながりを子どもに伝えることで、「両方やっている意味」が実感でき、どちらの習い事にも前向きに取り組めるようになります。相乗効果を見つけることは、両立をポジティブに続ける大きなエネルギーになります。


小さな進歩を具体的に褒める
子どものやる気を長く保つためには、「すごいね」「頑張ったね」といった抽象的な言葉よりも、成長のポイントを具体的に伝えることが重要です。たとえば、「前より音がそろってきたね」「今日は最後まで止まらずに弾けたね」「このフレーズの強弱がすごくきれいに出せたね」といった具合です。具体的な褒め言葉は、子どもに自分の成長をはっきりと感じさせ、「もっとできるようになりたい」という前向きな気持ちを引き出します。また、練習の過程での変化を褒めることで、「努力がちゃんと見てもらえている」という安心感が生まれ、ピアノと他の習い事を続けるエネルギーにつながります。
親も一緒に関心を持つ
子どもがピアノを続けやすくするには、親が演奏や練習に関心を持ち、日常的に関わることが大きな支えになります。練習を聴いて感想を伝える、弾いた曲について「どんな場面を思い浮かべたの?」と質問する、コンサートや音楽イベントに一緒に出かけるなど、関わり方はさまざまです。こうしたやり取りは「自分の努力を見てもらえている」という安心感を生み、子どものやる気を高めます。また、親が音楽に関心を持つ姿は自然と子どものお手本となり、ピアノと他の習い事を両立させるモチベーションを長く保つ力になります。
モチベーションを保つためには、成果を披露する場や、他の習い事とのつながり、小さな進歩を具体的に褒める工夫、そして親の関心と応援が欠かせません。こうした環境が整うことで、子どもは「自分は成長している」という実感を得られ、ピアノと他の習い事を前向きに続ける力が生まれます。周囲のサポートは、努力を支える土台であり、両立を楽しみに変える原動力になります。
無理をしない勇気と休息の価値
習い事を続けるうえで大切なのは、頑張り続けることだけではありません。ときには立ち止まり、休むことで心や体を整える時間が必要です。無理をしない勇気と休息の価値を知ることが、長く楽しく続けるための秘訣になります。
「疲れた」のサインを見逃さない
子どもは疲れやストレスを言葉でうまく表現できないことがあります。そのため、練習中に集中力が続かない、表情が硬い、ため息が増えるといった変化は「疲れた」のサインかもしれません。こうした兆しを感じたら、無理に続けさせず、短い休憩や気分転換を取り入れることが大切です。早めに休ませることで、ピアノそのものへの嫌悪感や燃え尽き感を防ぎ、次の練習への意欲を守ることにつながります。


休むことは後退ではない
休むことは決して後退ではなく、次に進むための準備期間です。練習を続けていると、心や体が疲れて思うように弾けなくなる時期がありますが、そこで思い切って休むことで、脳や筋肉が情報を整理し、技術が自然に定着することがあります。スポーツ選手が試合後に休養日を取るのと同じように、ピアノも回復の時間が必要です。「休む=サボる」ではなく、「次に良い演奏をするための充電」と捉えることで、休息は前向きな選択になります。
イベントの前後で調整する
発表会やコンクール、他の習い事の大会や試合など、大きなイベントの前後は生活リズムや練習内容を柔軟に調整することが大切です。イベント直前は集中力を必要とするため、無理に新しい曲に取り組むよりも、仕上げたい曲や得意な部分の確認に時間を使う方が安心です。逆にイベントが終わった後は、燃え尽きや疲れが出やすい時期なので、数日〜1週間程度は好きな曲を弾く時間や、練習時間を半分に減らす期間を設けると、次の目標に向けて気持ちを立て直しやすくなります。このように、前後の期間で強弱をつけたスケジュールを組むことが、長く続けるための余裕を生みます。
「やめない休み方」を身につける
とのつながりを保つ工夫です。たとえば、通常の練習はお休みにして、好きな曲を気軽に弾く時間だけにする、片手だけの練習や指ならし程度のスケールだけにする、といった方法があります。これなら心や体を休めながらも、鍵盤に触れる感覚を途切れさせずにいられます。また、演奏ではなく音楽を聴く時間を増やすのも効果的です。お気に入りの曲や発表会の録音を聴くことで、モチベーションが自然に回復することがあります。こうした「やめない休み方」を身につけると、一時的にペースを落としてもスムーズに元の練習リズムへ戻ることができ、ピアノと他の習い事を長く両立させる力になります。
無理をしない勇気と休息の価値を理解することは、習い事を長く続けるための大きな支えになります。疲れのサインを早めに察知して適切に休むことは、演奏力ややる気を守るための前向きな選択です。イベント前後の調整や「やめない休み方」を取り入れることで、心と体を回復させながら音楽とのつながりを保てます。休息は後退ではなく、次の成長へとつながる大切な時間です。
まとめ
ピアノと他の習い事を両立させるには、時間ややる気、体調の管理など、さまざまな工夫が必要です。これまで紹介した方法を組み合わせれば、無理なく続けられる環境が整い、子どもの成長を長く支えることができます。
目的と優先順位を家族で共有する
両立の土台は「なぜやるのか」を明確にすることです。ピアノも他の習い事も、それぞれの目的や意義を家族で話し合い、紙に書き出すなどして共有すると、迷ったときの判断基準になります。さらに、半年〜1年ごとに見直すことで、子どもの成長や興味に合わせて柔軟に方向を変えられます。これにより、途中で「やらされている感」が生まれにくく、本人も納得して続けられます。
細切れ時間とルーティン化で習慣を作る
練習は長時間よりも「毎日触れること」が大切です。5〜10分の短い時間でも、1日数回積み重ねれば十分な練習量になります。生活の流れの中に「おやつの前に1曲」「お風呂の前に音階」など固定の練習タイミングを作ると、迷わず続けられます。短時間でも効率的にするために、練習内容を絞り込み、その日のテーマを明確にすると効果が上がります。
モチベーション維持と休む勇気を持つ
やる気を保つためには、成果を披露する機会を積極的に作ることが効果的です。発表会や家族への演奏、友達とのお披露目会など、小さな成功体験が自信とやる気を生みます。また、他の習い事との相乗効果を意識し、それがピアノにも活きていることを本人に伝えると、両立の意義が実感できます。そして、疲れが見えたら迷わず休むこと。完全にやめるのではなく、好きな曲を短時間だけ弾くなど「やめない休み方」を取り入れ、心と演奏力の両方を守ります。


習い事の両立は、単に時間割をやりくりするだけの問題ではありません。大切なのは、子どもの成長に合わせて無理なく続けられる仕組みを作ることです。ピアノは感性や集中力を育て、音楽を一生の友にする力を与えてくれます。他の習い事も同じように、人生を豊かにする宝物です。「どちらかをあきらめなければならない」と思う必要はありません。目的を共有し、短い時間でも継続できる工夫をし、モチベーションを保ちながら時には休む勇気を持てば、両方をバランスよく続けられます。