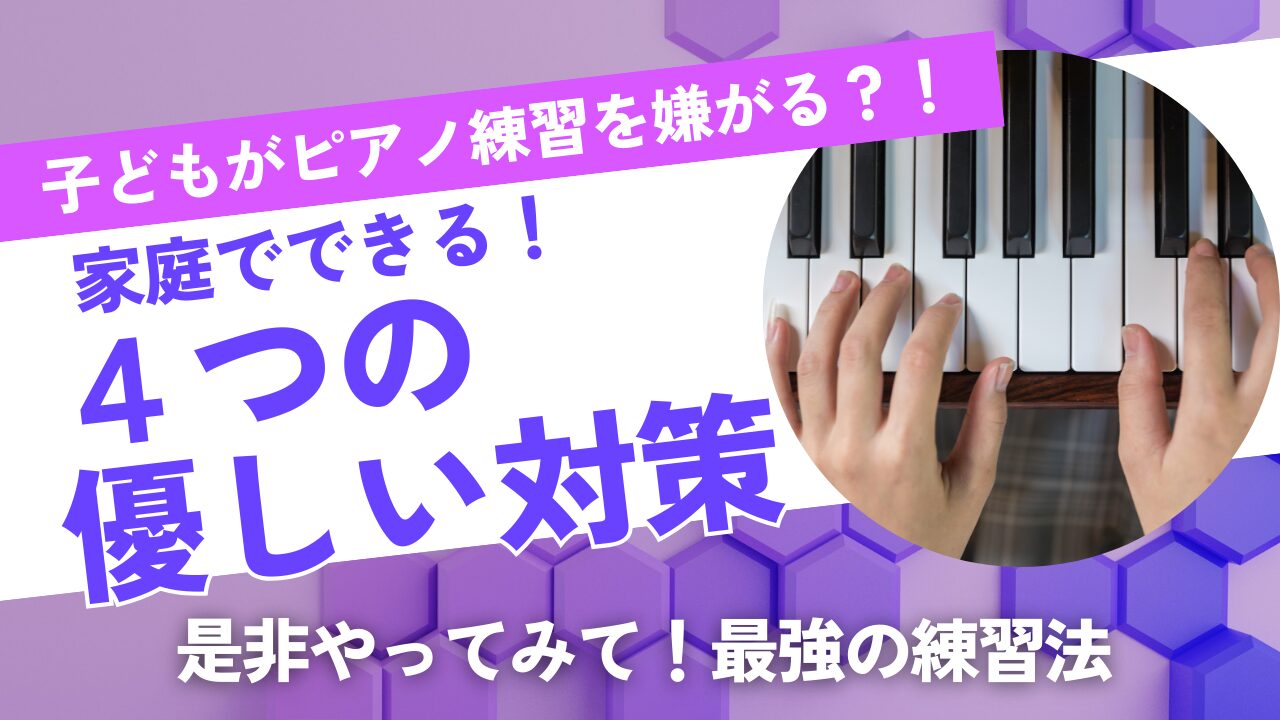「ピアノは好きなのに、練習となると嫌がる…」「声をかけるたびにケンカになってしまう…」そんな悩みを抱えるご家庭はとても多いです。ピアノの練習は毎日の積み重ねが大切ですが、子どもの気分や性格によっては「やりたくない!」という時期も必ずやってきます。大事なのは「練習をさせること」ではなく「自然にやりたくなる環境を整えること」。叱ったり無理強いしたりせずに、子どもの気持ちに寄り添いながら楽しく続ける工夫が必要です。この記事では、練習を嫌がる子どもへの4つの具体的な対策をご紹介します。

練習を嫌がる子供にどうやって声をかけるか悩むわ
練習時間を短く区切ってハードルを下げる
子どもがピアノの練習を嫌がる大きな理由のひとつに「長くやらされるのがイヤ」というものがあります。集中力が続かない年齢なのに「30分やりなさい」と言われると、それだけで気持ちが重くなってしまうのです。だからこそ、練習のハードルを下げて「これならできそう」と思える工夫が大切です。
まずは「5分だけ」でOKにする
最初から長時間を求めず、「今日は5分だけ」「1曲だけでいいよ」と区切って声をかけましょう。子どもは「これくらいならできる」と思えて、嫌な気持ちが和らぎます。実際に始めると気分が乗って、自然に予定より長く練習することも少なくありません。
タイマーや砂時計を使って楽しく時間を区切る
「あと何分」と言われるより、目で見て時間を感じられる工夫をすると、子どもは取り組みやすくなります。砂時計やキッチンタイマーを使って「この砂が落ちるまでやってみよう」とするだけで、遊び感覚で練習が進むこともあります。
1日の中で何回か小分けにする
30分を一度にまとめて練習するのではなく、10分を朝・夕方・夜などに分けるのも効果的です。短い時間なら集中しやすく、無理なく習慣化できます。「勉強の前にちょっと弾こう」「お風呂の前に5分だけ」など、生活の流れに組み込むのもおすすめです。


「短くても続ける」ことを大切にする
練習は量よりも「毎日の積み重ね」が大切です。たとえ5分でも毎日鍵盤に触れることで、感覚が身につき、やめ癖がつきにくくなります。親としては「短いけど今日はできたね」と認めてあげることが、子どもの自信ややる気を育てます。
子どもにとって「練習=長くて大変」というイメージがついてしまうと、嫌がる気持ちは強まってしまいます。短く区切ることで「これならできる」という成功体験を積み重ねれば、練習が自然と日常に溶け込んでいきます。無理に時間を延ばすよりも、短くても楽しく続けることが、長い目で見て一番の上達につながるのです。
練習を“遊び感覚”に変える
子どもが練習を嫌がる理由のひとつは、「練習=つまらない」「やらされている」というイメージがついてしまうことです。これを逆に「練習=遊び」と感じられるように工夫するだけで、子どものやる気はぐんと変わります。音楽は本来楽しいもの。少しの仕掛けで、練習時間を遊びの延長に変えてあげることができます。
シールやポイントで「ゲーム化」する
練習ができたらシールを貼る、ポイントを貯めると小さなご褒美がもらえるなど、ゲーム感覚を取り入れると「やりたい!」という気持ちが生まれます。子どもは成果が目に見えると喜びや達成感を感じやすく、それが次の練習の原動力になります。
曲をクイズや遊びに変える
例えば「この曲を10回弾いたらおしまいゲーム」「わざと音を間違えないで弾けるかな?」といったクイズ形式にするだけで、同じ練習でも楽しさが増します。兄弟や家族と一緒に「先生役」「生徒役」を交代して遊ぶのも効果的です。
親子で一緒に参加する
子ども一人に「練習しなさい」と言うより、親も一緒に歌ったりリズムを取ったりするだけで雰囲気が和みます。「一緒に遊んでいるうちに気づいたら練習になっていた」という流れが作れると、嫌がる気持ちが自然に和らぎます。


道具やアイデアで新鮮さを出す
練習カードやカラフルなタイマーを使う、録音して自分の演奏を聴いてみるなど、ちょっとした工夫で子どものモチベーションは上がります。変化をつけることで「今日は何をするのかな?」とワクワクする気持ちを引き出せます。
「練習を遊びに変える」ことは、決して甘やかすことではありません。むしろ、子どもにとって自然に音楽を好きになるための大切な工夫です。遊びのように取り組めると、練習が習慣になり、やがて「楽しいから続けたい」という自発的な気持ちにつながります。音楽の楽しさをそのまま練習に生かすことが、長く続ける秘訣です。
親が共感し、寄り添う声かけをする
子どもが練習を嫌がるとき、一番大切なのは「どう声をかけるか」です。強く叱ったり「やりなさい」と命令口調になると、ますますやる気をなくしてしまいます。逆に「気持ちをわかってもらえた」と感じられると、子どもは安心して練習に向かうことができます。親の声かけひとつで、練習が“イヤな時間”にも“楽しい時間”にも変わるのです。
まずは気持ちを受け止める
「やりたくないんだね」「今日は疲れているのかな」と、子どもの気持ちを否定せずに言葉にしてあげるだけで、子どもは安心します。「分かってもらえた」と感じることで、心のハードルが下がります。


小さな選択肢を与える
「今すぐやる?それとも夕ご飯のあとにする?」といった小さな選択を与えると、子どもは自分で決めた気持ちになり、前向きに取り組みやすくなります。「やらされている」感覚を減らす工夫です。
共感と励ましをセットで伝える
「難しい曲だから大変だよね。でも昨日より上手になってるよ!」というように、子どもの大変さを認めつつ、できている部分を励ましてあげましょう。共感とポジティブな言葉がセットになると、やる気につながります。
親子で「小さなゴール」を共有する
「今日は最初のフレーズだけ弾けたら終わりにしよう」など、親子で小さな目標を決めて取り組むと、達成感を分かち合えます。子どもにとって「お母さん(お父さん)と一緒にできた」という経験は、安心と自信につながります。
子どもが練習を嫌がるとき、無理にやらせるのではなく「気持ちを理解してあげること」が第一歩です。親が共感し、寄り添う声かけをするだけで、練習は押しつけから「安心できる時間」に変わります。叱るよりも理解して励ます――それが、子どもがピアノを楽しく続けるための何よりのサポートです。
小さな達成を積み重ねて自信を育てる
子どもが練習を嫌がるとき、「できた!」という達成感が不足していることが多いです。いきなり大きな課題や長い曲を求められると、自信を失って「やりたくない」と感じてしまいます。だからこそ、毎日の練習の中で「小さな成功体験」を積み重ねることが大切です。
ゴールを小さく設定する
「今日は1段だけ弾けたらOK」「右手だけ通せたら終わり」といった、小さなゴールを設定してあげると、達成感を味わいやすくなります。ゴールを細かく分けることで「できた!」の回数が増え、子どもは自信を持ちやすくなります。
できた瞬間をすぐに褒める
小さな進歩でもその場で「今のすごくきれいに弾けたね」と言葉にすると、子どもは達成感を強く実感します。褒められることで「次も頑張ろう」という気持ちが自然に生まれます。
記録して「見える化」する
練習した日をカレンダーにシールで残したり、動画に撮って後で一緒に見返したりするのも効果的です。「昨日よりできるようになった」という事実を自分の目で確認できると、自信が積み重なります。
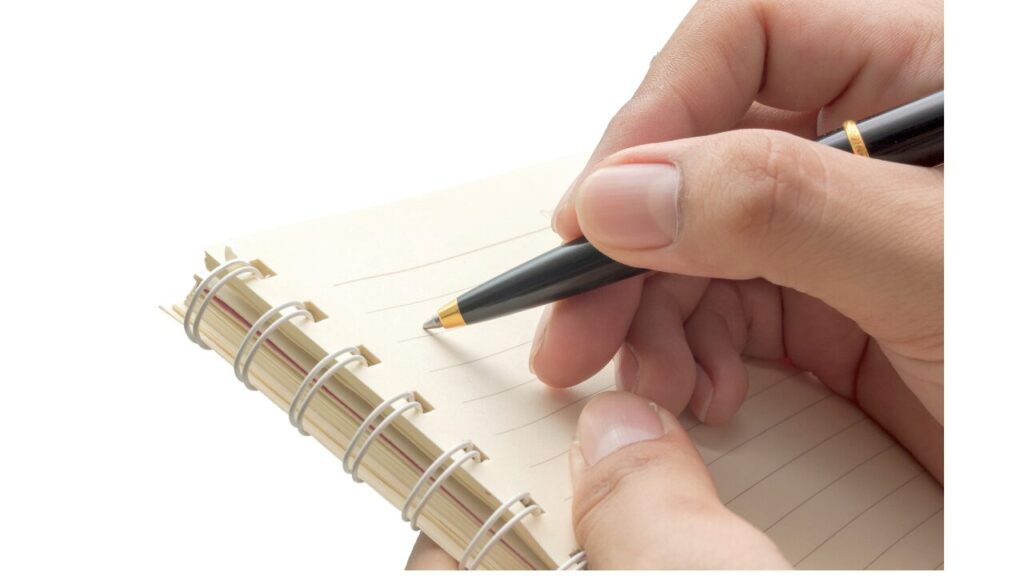
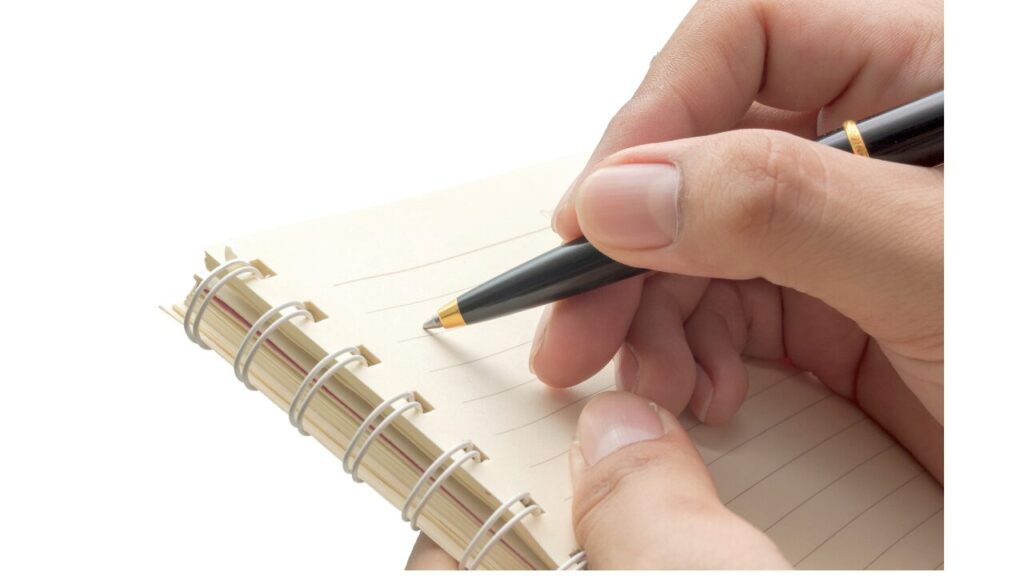
成果を家族と共有する
「今日はここまで弾けたよ」と家族に披露する時間を持つのもおすすめです。小さな演奏会のように褒めてもらうことで、子どもは「やってよかった」と思え、練習を前向きに続けるエネルギーになります。
子どもにとって、自信は練習を続ける一番のエネルギーです。小さな達成を日々積み重ねることで「できた!」という喜びが育ち、それが「もっと弾きたい」という意欲につながります。大きな成長のためには、まずは小さな一歩。その積み重ねこそが、子どもがピアノを楽しみながら上達する力になります。
まとめ
子どもが練習を嫌がるのは特別なことではなく、どの家庭でも必ず直面する自然な姿です。大切なのは「嫌がらないようにさせること」ではなく、「嫌な気持ちを和らげて自然に練習につなげる工夫」をすることです。
ハードルを下げて「やれる気持ち」を作る
長時間を求めず、5分だけ・1曲だけと小さく区切ることで、練習を始めやすくなります。短くても続けることが習慣化につながります。
練習を「遊び」として取り入れる
シールやゲーム感覚、親子のやりとりなどを通して、練習そのものを楽しい体験に変えると、子どもは自然にピアノに向かいます。
小さな達成を認めて自信を育てる
「できた!」という成功体験を積み重ねることで、子どもはピアノに前向きになり、自分から練習したいという気持ちが育ちます。


子どもが練習を嫌がるときこそ、親の寄り添い方や工夫が大切です。無理にやらせるよりも「短くてもいい」「楽しくできた」「できたね!」と認めることで、ピアノは子どもにとって安心できる居場所になります。練習は苦しみではなく、音楽を楽しむための時間。子どもが笑顔で続けられる工夫を、家庭で温かくサポートしてあげましょう。