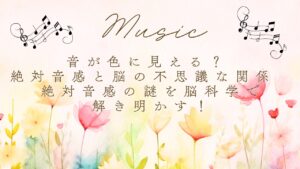皆さんの中で絶対音感に憧れたことはありますか?絶対音感は、他の音を聞かなくとも、突然聞こえてきた音の高さがわかる能力であり、例えば、ドの音が聞こえたときに、それがドの音だと判別できることです。しかも、音階を正確に記憶しているので、瞬時に何の音なのか分かると言います。また、相対音感というものもあり、相対音感とは、絶対音感とは違い、基準の音を聞いたら、その音と比べて他の音の高さを判別することです。この絶対音感ですが、イメージとしては限られた人のみが手にすることができる生まれつきの才能のように考えがちかもしれません。しかし、絶対音感は遺伝で身につくものではなく、実は後天的なもの、鍛えれば習得できる能力なのです。習得するためには、相対音感が発達する前の3〜5歳の間に訓練をする必要があります。7歳前後になると身に付けにくいと言われています。今回はそんな絶対音感をもっている方の割合と、音楽に役たつ本当の音感とは何かを詳しく解説していきます。
 平田先生
平田先生絶対音感に興味がある方はぜひ読んでみて下さい!
絶対音感をもっている方の割合
周りに「絶対音感をもっている」という方はいらっしゃるのではないでしょうか。調査統計では、0.2から0.5%が“絶対音感保有者”ですが、直感的にはもっと多くいる印象があります。知人の中に“絶対音感保有者”がいるということも、決してめずらしくありません。正しい割合を環境別にみてみましょう。
生まれつきの場合
生まれつき絶対音感をもっているという方は20万人に1人と言われ、割合は0.0005%ほどと大変珍しい才能である事がわかっています。これは生まれつきの場合であることを覚えていて下さい。
楽器演奏を専門にしている方や、音大生の場合
音楽を専門として日常的に行っている方や、音楽学生であれば大体5~6割の人が絶対音感を持っている、と言われています。これは幼い時から継続的に音感教育を行い聴覚が発達していることから言えます。


一般の方の割合
一般の人で絶対音感を持っている割合は、大体3%くらいと言われています。100人いれば3人は絶対音感を持っている人がいるということですね。これは、幼い頃、音感教育を受けた、ピアノを習っていたなどの経歴がある事が、ほとんどで、絶対音感は聴覚の発達時に何らかの音感教育の習慣を行っていたと考えられます。
日本人と外国人の絶対音感の割合
日本、中国、ポーランドの音大生を集めて絶対音感についての調査を行った研究があります。結果、90パーセント以上の正答率だった生徒は、日本約6割、中国約2.5割、ポーランド約1割(ショパンの生まれた国)と言う結果だったそうです。他にも、西洋諸国は絶対音感の割合が低いと言う記事があります。
絶対音感を持っている方の環境はさまざまで、おかれた環境で割合が変わることがわかりました。一般的に希少な才能と言われているのは、生まれつき絶対音感を持っている人のことを指し、音楽環境にいる人や、音楽教育を受けた人が持っている割合は増えることもわかりました。
絶対音感は生まれつきではない?
絶対音感は「生まれつきではない」という見方が一般的であり、その理由は次のような理由です。
幼少期の環境要因
絶対音感は、幼少期(特に3~6歳)の感受性が高い時期に音楽教育を受けることで発達する可能性が高いとされています。この時期に訓練を受けた子供が絶対音感を獲得しやすいことが多く、遺伝的な要因よりも環境的な要因が重要視されています。


後天的な学習の影響
絶対音感の訓練プログラムが成功している例が多く報告されています。これにより、遺伝だけでは説明できず、訓練や学習によって能力を後天的に獲得できることが示されています。
文化的影響
日本や韓国のように幼少期の音楽教育が普及している地域では、絶対音感を持つ人が相対的に多いとされています。一方で、音楽教育の形式が異なる地域では、絶対音感の保持者が少ない傾向が見られます。このことから、絶対音感は文化的・教育的な背景に依存することが分かります。
遺伝的な証拠の不足
絶対音感を持つ人が家族内に多い場合がありますが、それが必ずしも遺伝によるものではなく、家族内での音楽教育環境や習慣が影響している可能性が指摘されています。また、遺伝的な研究でも、直接的に絶対音感を司る遺伝子は特定されていません。
絶対音感は、幼少期の適切な環境や訓練が重要である後天的な能力であると考えられます。
絶対音感は必ず有効な音感ではない?!
絶対音感は1つの聴力の才能です。生まれつき持ち合わせた人の割合を見るとそれは神秘的な能力かもしれません。しかしその割合の神秘性から、絶対音感を「神の能力」「最強の能力」と思っている方も多いです。
絶対の音感?
日本では絶対音感の絶対とは、完璧、素晴らしい、という意味に取られることが多い気がします。しかし絶対音感の絶対とは「他と比べることのない絶対的な聴き方」の「絶対」の意味を持ちます。ですから特別に「素晴らしい」とか、「完璧」とかの価値観はないということです。
絶対音感をめぐる誤解
一般的に、例えば「ラ」と言う音は1つしかないと思われがちですが、実はそうではありません。音の振動数を表すヘルツでいうと、現代のラは440Hzと国際基準では定められています。しかし実際438Hzになってもラです。吹奏楽などでは、「ラ」を442Hzにする場合もあります。440Hz付近のヘルツは大体ラなのです。ちなみにバッハなどの時代にですと415Hzがラと言う音でした。これは実際に聴いてみるとかなりの差で、半音近い差があります。つまり400年前のラの音は今のラ♭の音ということになります。しかし、絶対音感をもっている人は、「440Hzがラだ!」と認識します。(正しい絶対音感トレーニングで習得した人はそうはなりません)つまり、数Hz違う音でも違和感を感じてしまいます。ところで、クラシック音楽の現場では、それぞれの作曲家ごとにラのピッチが変わります。現代作曲家なら440や442Hz。バロック音楽なら415Hzなど。音感のない人でさえ、半音の違いは鮮明に認識できるほどですから絶対音感がある人はかなりの差に違和感を感じることは想像に難くありません。と言うことは、絶対音感はむしろ音楽活動の妨げになってしまうこともあるということです。


絶対音感と相対音感
絶対音感を持っている人の割合が少ないがゆえに、何よりも優れた能力と思われがちですが、前述した相対的な聴き方ができる相対音感の能力も備わってこそ音楽活動は有利になってきます。
絶対音感にも時として困った場面もあるんですね。絶対音感が存在する割合が少数=最強の能力ではないこともあります。
絶対音感をつけたいならピアノがおすすめ
絶対音感を身につけるにはピアノがおすすめされることが多いです。その理由を4つ挙げます。
正確な音程が保証されている
ピアノは一度調律されると、鍵盤を押すだけで正確な音程が出ます。他の楽器では演奏者の技術や環境により音程が微妙に変化することがありますが、ピアノでは常に正しい音が出るため、絶対音感の訓練に適しています。
広い音域にアクセスできる
ピアノは88鍵もの幅広い音域をカバーしており、高音から低音まで幅広い音に触れることができます。これにより、様々な音に慣れることができ、絶対音感の習得に必要な音の多様性を効率的に学べます。
視覚的な学習が可能
ピアノでは鍵盤の並びが視覚的に分かりやすく、音程感覚を身につける際に役立ちます。例えば、白鍵と黒鍵の配置が規則的で、音名や音程を視覚的に理解しやすいので、聴覚だけでなく視覚の助けも借りられます。


同時に複数の音を練習できる
ピアノでは一度に複数の鍵を押して和音(複数の音)を出すことができるため、単音だけでなく音の組み合わせを覚える訓練が可能です。これにより、音を識別する能力がさらに高まり、絶対音感を効率よく養うことができます。
ピアノは正確な音程、広い音域、視覚的な学習要素、そして複数の音を扱う能力を兼ね備えており、絶対音感をつけるための最適な楽器と言えます。
まとめ
絶対音感は生まれつきなのか、音楽活動にとって有利な音感はなんなのかをお話ししてきました。簡単にまとめてみます。
絶対音感は生まれつきではない
絶対音感は生まれつきではなく、幼少期の感受性が高い時期に音楽教育や訓練を受けることで身につく能力です。環境や学習が重要な役割を果たしており、遺伝的要因よりも後天的な影響が大きいとされています。
絶対音感は必ずしも有効な音感ではない
絶対音感は必ずしも有効な音感ではなく、音楽の実践では音程の関係性を重視する相対音感の方が役立つ場面が多いです。また、絶対音感を持つ人は音のズレに敏感すぎるため、音楽を楽しむ妨げになることもあります。
絶対音感をつけたいならピアノがおすすめ
絶対音感をつけたいならピアノがおすすめです。ピアノは正確な音程を出せるうえ、広い音域に触れることができ、鍵盤で音を視覚的に学べるため、効率よく訓練ができます。


絶対音感が素晴らしい才能の1つであることは確かですが、それは生まれつきや、1番の才能でもないことということです。