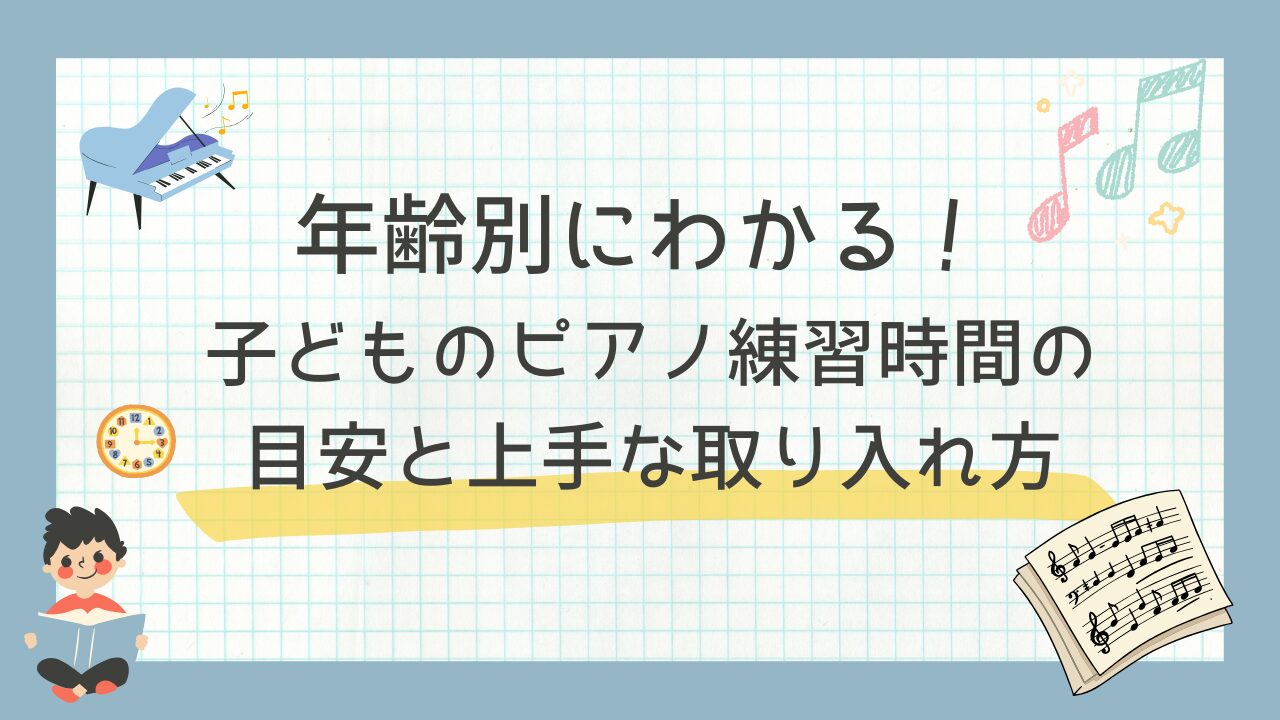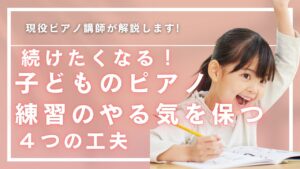ピアノを習い始めたとき、多くの保護者が悩むのが「毎日の練習、どのくらいやればいいの?」という点です。練習時間が短すぎると上達が遅れるのでは…と不安になったり、反対に長すぎて子どもが嫌にならないかと心配になったり。実は、年齢や成長段階に応じて適切な練習時間は変わってきます。大切なのは「長さ」よりも「内容」と「習慣」。この記事では、子どもの年齢ごとに目安となる練習時間と、家庭で取り入れやすい工夫についてご紹介します。

子供への明確な練習時間が知りたいわ!
幼児期(3〜6歳)は時間より回数が効果的
ピアノを習い始めたばかりの幼児期にとって、長時間の練習はかえって逆効果になることがあります。集中力が続くのはせいぜい数分間。無理に長く練習させようとすると、ピアノに対して「楽しい」よりも「嫌だ」という気持ちが強くなってしまいます。大切なのは量ではなく「質」。この時期は1日5〜10分でも十分であり、その中で「楽しい」「できた!」という気持ちを育てることが何よりの目標です。
短時間で達成感を味わえる練習
幼児は「やった!できた!」という感覚を大事にしています。そこで「今日はドとレを弾いてみよう」「このリズムを一緒に叩いてみよう」と、短く区切った目標を与えることが効果的です。5分間でもその中で達成感を得られれば、子どもの心に「ピアノは楽しい」というイメージが残ります。
遊びの延長としての練習スタイル
幼児期の練習は「机に向かって勉強する」感覚では続きません。歌を歌ったり、動物の鳴き声を真似して音を出したりするなど、遊びとつなげることで夢中になれます。例えば「ライオンの声は低い音!」「鳥の声は高い音!」といった遊び心を取り入れると、音の高低を自然に理解でき、楽しみながら学べます。
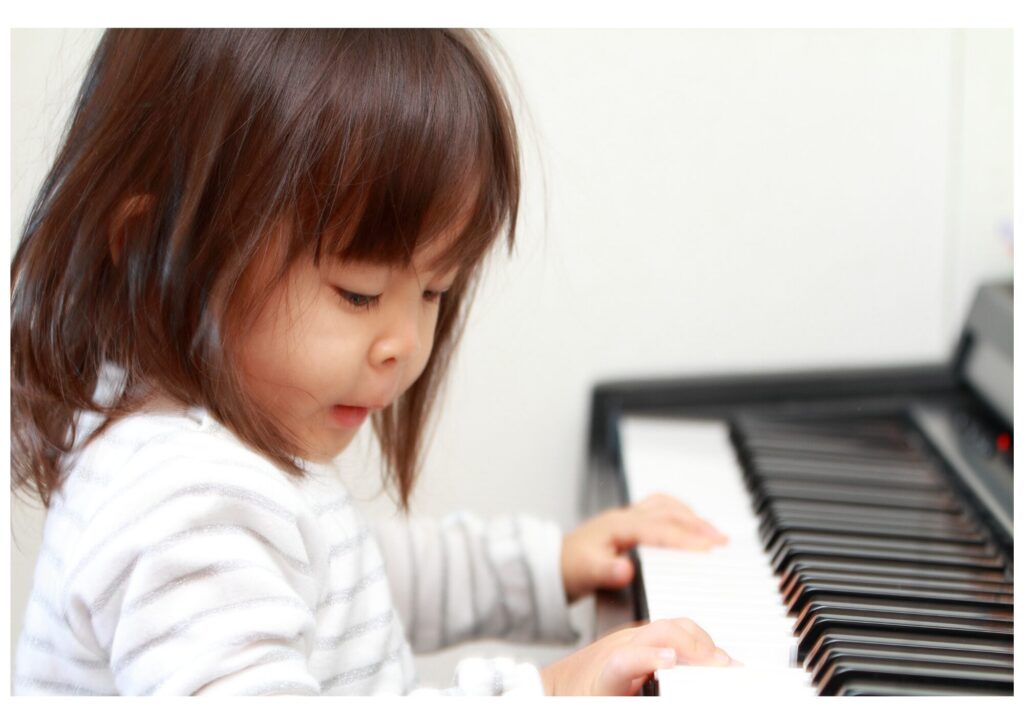
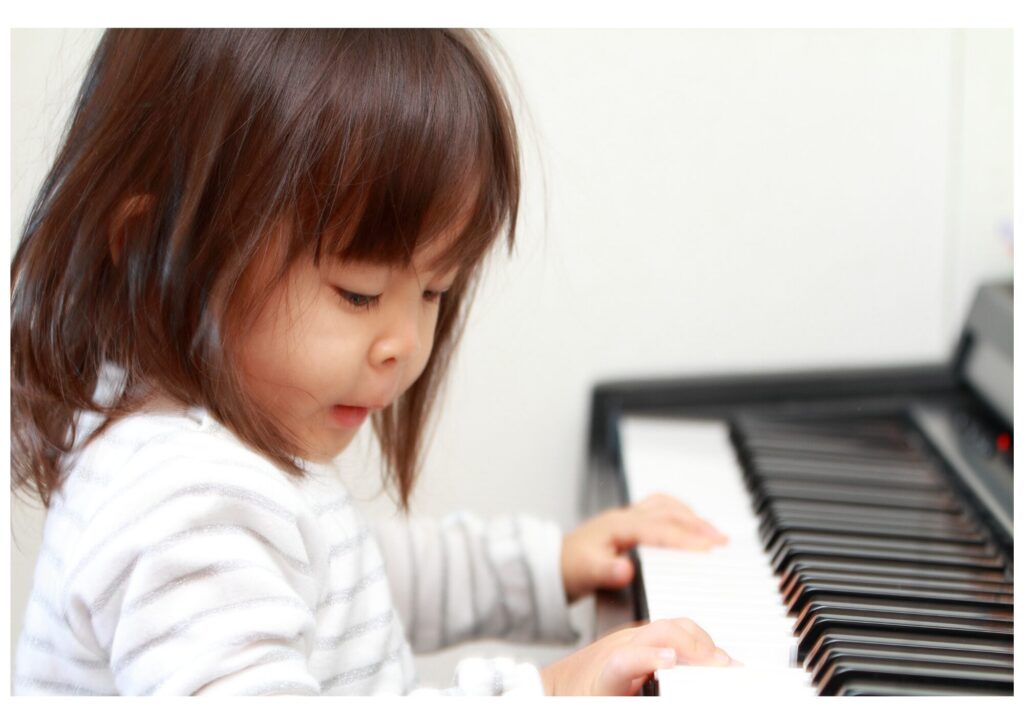
毎日少しずつ、習慣をつける
たとえ短時間でも「毎日ピアノに触れる」ことが大切です。毎日同じ時間に5分取り組むだけで、子どもは「ピアノは生活の一部」として自然に受け入れられます。逆に「時間があるときにまとめて練習」では習慣化できず、ピアノが身近な存在になりにくいのです。短いけれど毎日の積み重ねが、将来の基礎力になります。
保護者の関わりで楽しい時間にする
幼児期の子どもは一人では練習を進めにくいため、親の関わりが欠かせません。「すごい!ドの音を探せたね」と具体的に褒めてあげると、子どもは誇らしげな気持ちになります。また、親も一緒に歌ったり手をたたいたりすることで、練習は「親子の楽しい時間」へと変わります。この安心感が「またやりたい」という気持ちを引き出します。
幼児期のピアノ練習は「長さ」ではなく「楽しさ」と「習慣」が大切です。5〜10分という短い時間の中で達成感を味わい、遊びを取り入れ、毎日続け、保護者と一緒に楽しむ――この4つを意識すれば、子どもは自然にピアノを好きになり、長く続けるための土台が育ちます。「短くても毎日続けること」が、幼児期における最良の練習法なのです。
小学生低学年は「10〜15分」で習慣づけ
小学校に入ると、子どもは少しずつ集中力が伸び、学習や習い事に取り組む姿勢も安定してきます。しかしまだ長時間の練習をこなせる段階ではありません。この時期に大切なのは「毎日ピアノに向かう習慣をつけること」。1日10〜15分程度の短い練習でも、続けることで基礎がしっかりと身につき、練習を自然に生活の一部として受け入れられるようになります。
短時間でも「毎日続ける」ことが大切
10〜15分という時間は、低学年の子どもにとって無理のない長さです。大切なのは「やった時間」よりも「毎日ピアノに触れる」という習慣。週に一度30分まとめて練習するよりも、毎日10分の積み重ねの方がずっと効果的です。
回数を分けて取り入れると効果的
学校や宿題で疲れている日は、10分間続けるのが難しい場合もあります。そんなときは朝5分、夕方5分と分けて取り入れても構いません。練習に触れる「回数」が増えることで、音や指の感覚が自然に体に定着していきます。
「今日はここまで」という小さなゴールを決める
低学年の子どもには「ただ練習する」よりも「今日の目標」を決めた方が達成感を得やすいです。たとえば「この小節を間違えずに弾けるようにする」「両手で最後まで通してみる」といった小さなゴールを設定すると、10分でも充実した練習になります。
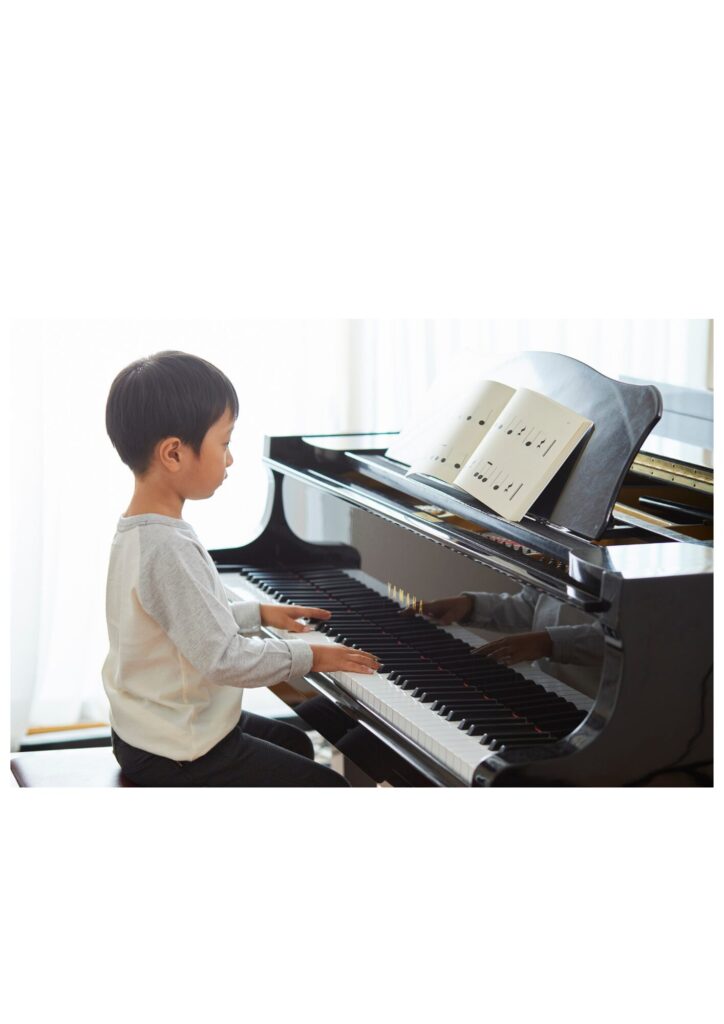
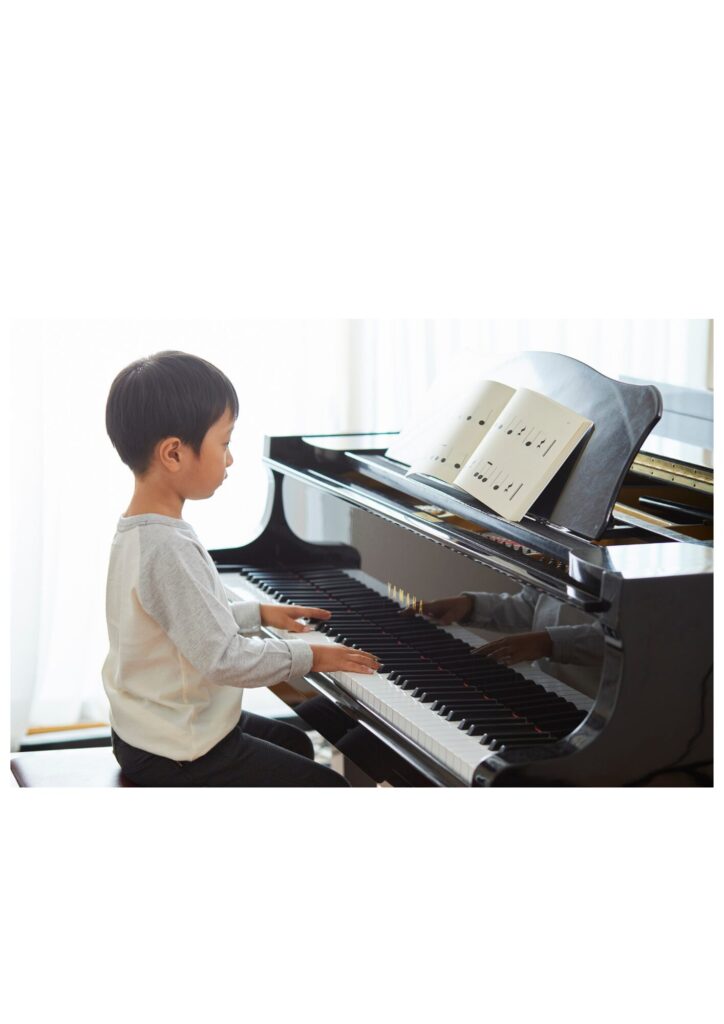
親が見守りつつ自立を促す
この時期は、子どもが一人で練習に向かうようになる大事な時期です。ただし完全に任せてしまうとまだ不安定なので、最初は保護者が「今日はここからやろうね」と軽く声をかけたり、終わったら「よく頑張ったね」と具体的に褒めてあげることが効果的です。少しずつ自分から取り組む姿勢を育てていくことが、将来の継続につながります。
小学生低学年にとって、練習の目安は「毎日10〜15分」。その短い時間をどう過ごすかがポイントです。毎日続けること、回数を分けて無理なく取り入れること、小さなゴールを設定すること、そして親が見守りながら自立を促すこと。この4つを意識すれば、練習は自然に習慣となり、楽しみながら力を伸ばしていけます。練習時間の長さにこだわるよりも「毎日の積み重ね」を大切にすることが、この時期の子どもにとって一番の上達の近道です。
小学生高学年は「20〜30分」で基礎力を強化
小学校高学年になると、集中力や理解力がぐっと高まり、曲の難易度も上がってきます。両手での演奏が自然になり、ペダルを使ったり表現を工夫したりと、演奏に幅が出てくる時期です。その一方で、学校生活が忙しくなり、練習に割ける時間が限られてくる子も少なくありません。この年代で意識したいのは「20〜30分の練習で基礎をしっかり固める」こと。効率よくポイントを押さえた練習で、音楽的にも技術的にも大きく成長できます。
ウォーミングアップで指を育てる
高学年になると指の独立性や柔軟性が必要になります。いきなり曲を弾くのではなく、スケールやハノンなどの基礎練習から始めることで、手の形や指の力が整います。5分程度のウォーミングアップを取り入れるだけで、曲の仕上がりも大きく変わります。
部分練習で効率を高める
20〜30分の中で曲を最初から最後まで通すだけでは、なかなか定着しません。特に弾きにくいフレーズや間違えやすい部分を数分間集中して練習することが大切です。部分をしっかり固めた上で全体を通すと、安定感のある演奏につながります。


通し練習で集中力を養う
部分練習だけでなく、仕上げとして全体を通して演奏する時間も設けます。ここで大切なのは「止まらず最後まで弾くこと」。多少のミスがあっても、演奏を続ける力は発表会やコンクールで大きな武器になります。通し練習の習慣は、集中力や表現力を磨く土台になります。
毎日の積み重ねで表現力を育てる
20〜30分という練習時間を毎日続けることで、技術だけでなく音楽表現の幅も広がっていきます。「今日は強弱を工夫してみよう」「このフレーズは歌うように弾こう」といった小さなテーマを持つと、ただ弾くだけの練習から「音楽をつくる練習」へと変わります。高学年は表現力が伸びる時期でもあるため、この工夫が上達に直結します。
小学生高学年の練習は「20〜30分」が目安。ウォーミングアップで指を整え、部分練習で弱点を克服し、通し練習で集中力を養い、表現力を意識して音楽を楽しむ。この4つをバランスよく取り入れることで、限られた時間の中でも大きな成長が得られます。この時期に身につけた基礎力は、中学生以降の高度な演奏へとつながるかけがえのない財産となるのです。
中学生以降は「30分以上」で表現力を育てる
中学生になると、身体的にも精神的にも大きく成長し、音楽の理解力や集中力も格段に高まります。一方で、部活動や勉強との両立が必要になり、練習時間を確保することが難しくなる子も多い時期です。だからこそ「限られた時間の中で質の高い練習をすること」と「表現力を育てること」が重要になります。最低でも30分以上を目安に、基礎の確認と表現の探求をバランス良く取り入れることが、この年代での成長につながります。
基礎練習を怠らずに取り入れる
高度な曲に挑戦するようになっても、スケールやアルペジオ、指の独立を育てるエチュードなどの基礎練習は欠かせません。10分程度でも良いので、毎回必ず基礎練習を取り入れることで、難しい曲をスムーズに弾く土台ができます。中学生以降は「基礎を維持しながら曲に活かす」意識を持つことが大切です。
曲の理解を深めて音楽的に仕上げる
小学生までは「弾けるようになること」が主な目標でしたが、中学生になると「どう弾くか」が重要になります。曲の背景や作曲者の意図を知り、強弱やテンポの変化を意識しながら練習することで、音楽に深みが生まれます。30分以上の練習時間の中で「表現を探る時間」を設けると、演奏が大きく成長します。
通し練習で持久力と集中力を養う
演奏会やコンクールを意識するなら、長い曲を最後まで集中して弾き切る力が必要です。通し練習は20分以上の練習の中で必ず取り入れましょう。「途中で止まらない」「最後まで音楽を流れでつなげる」という意識を持つことで、本番の強さが身につきます。


自分の音を客観的に聴く習慣を持つ
この時期は自己表現の幅が広がる反面、客観的に自分の演奏を捉える力が不足しがちです。録音や録画をして自分の音を聴き返す習慣をつけると、改善点や表現の可能性に気づけます。先生のアドバイスに頼るだけでなく、自分で課題を発見して修正できるようになると、成長のスピードが格段に上がります。
中学生以降の練習は「30分以上」が目安。基礎練習を続けながら、曲の表現を深め、通し練習で集中力を養い、自分の演奏を客観的に見直す――この4つを意識することで、技術だけでなく音楽性も大きく育ちます。この時期に培った「自分の音を考え、表現する力」は、将来にわたってピアノを楽しむためのかけがえのない財産となるでしょう。
まとめ
子どものピアノ練習は「長ければ良い」「短いと効果がない」というものではありません。大切なのは、その子の年齢や発達段階に合わせて無理なく続けられる練習を積み重ねることです。練習時間の目安を知っておくことで、保護者も安心してサポートでき、子どももピアノを楽しく続けやすくなります。
幼児期は「短く楽しく」を最優先に
3〜6歳は集中力が短いため、1日5〜10分でも十分です。遊びの延長で楽しくピアノに触れる経験を積み重ねることが、将来の基礎につながります。
小学生は「習慣化」を意識する
低学年は10〜15分で毎日の習慣を定着させ、高学年は20〜30分の中で基礎力を強化していきます。時間よりも「毎日ピアノに触れる回数」が重要で、短い練習を生活の一部に取り入れることが効果的です。
中学生以降は「質と表現力」を大切に
30分以上の練習を確保しつつ、基礎練習に加えて曲の表現や音楽的な理解を深めることが大切です。録音や通し練習を取り入れることで、自分の演奏を客観的に見直す力も育ちます。


子どものピアノ練習において大切なのは「長さ」ではなく「質」と「習慣」です。幼児期は短く楽しく、小学生は毎日の習慣を定着させ、中学生以降は表現力を深める――このように年齢ごとに練習の在り方を工夫することで、子どもは無理なくピアノを続け、音楽を一生の友にすることができます。保護者は「練習時間を管理する人」ではなく「ピアノを楽しく続けられる環境をつくるサポーター」であることを意識すると、子どもも安心して成長していけます。