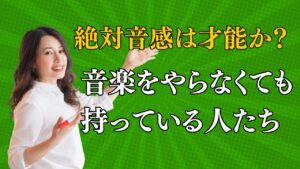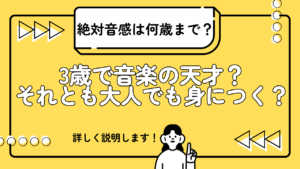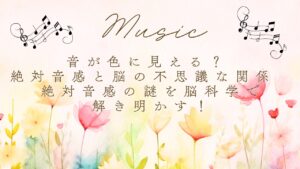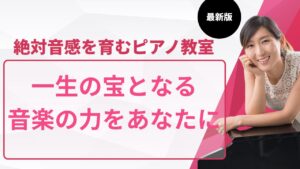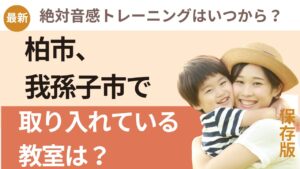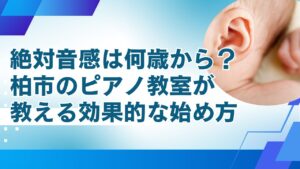「ドレミファソラシド」と聞いたとき、どの音かわかりますか?もし、音を聞くだけで正確に名前を言い当てられるなら、それは“絶対音感”の可能性があります。絶対音感とは、基準音がなくても音の高さを正しく判断できる能力のこと。この能力は、幼少期からの訓練によって身につくことが多いといわれていますが、大人でもある程度の音感を持っている場合もあります。もしかすると、あなたにも隠れた才能があるかもしれません!今日は、簡単にできる「絶対音感チェック」の方法と、絶対音感の仕組みについてご紹介します。
 平田先生
平田先生私が詳しく解説します!
絶対音感とは?相対音感との違い
音楽を学ぶうえで、「絶対音感」と「相対音感」という言葉を耳にすることがあります。これらはどちらも音を聞き分ける能力ですが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。ここでは、絶対音感と相対音感の違いについて、4つのポイントに分けて詳しく解説します。
絶対音感とは?音を“そのまま”認識する能力
絶対音感とは、基準となる音を聞かなくても、単独の音を聞いただけでその音の名前を即座に判断できる能力のことを指します。例えば、ピアノの「ソ」の音を聞いたときに、「これはソだ」と瞬時に認識できる人が絶対音感を持っていると言えます。これは、音の高さをまるで色のように“固定されたもの”として記憶し、識別する力です。絶対音感を持つ人は、楽器の音だけでなく、日常の音(車のクラクション、電子レンジの音など)も音名として聞こえることが多いとされています。
相対音感とは?音の“関係”を認識する能力
相対音感とは、一つの基準となる音を聞いたうえで、その音との“音程の違い”を判断する能力のことです。例えば、「ドの音」を基準として与えられたときに、そのあとに鳴った音が「ミ」だと分かるような感覚です。この能力を持つ人は、音楽を聴く際に「メロディーの動き」や「音と音の間隔」を捉えることができます。実は、音楽を演奏したり、作曲をしたりする際には、絶対音感よりも相対音感の方が実用的だと言われることもあります。
絶対音感と相対音感の習得時期の違い
絶対音感は、主に幼少期(3〜6歳頃)までに適切な音楽教育を受けることで習得できるとされています。この時期にピアノや楽器の音を聞きながら、音の名前を繰り返し学ぶことで、脳が音を記憶し、音名を瞬時に判断できるようになります。一方、相対音感は大人になってからでも習得可能であり、訓練によって向上させることができます。例えば、ソルフェージュ(音感トレーニング)を行うことで、音と音の間隔を正確に感じ取る力を養うことができます。


絶対音感と相対音感のメリット・デメリット
それぞれの音感には、長所と短所があります。
絶対音感のメリット
- どんな音でも瞬時に判別できるため、耳コピが得意
- 楽器のチューニングを正確に行える
- 聴いただけで楽譜に書き起こすことができる
絶対音感のデメリット
- 半音ズレた音(ピッチの違い)に敏感すぎて気になりやすい
- すべての音が音名で聞こえるため、雑音が気になりやすい
- 絶対音感があっても、音楽的な表現や和音の響きを感じる力とは別の能力である
相対音感のメリット
- 楽譜がなくても、基準音さえあれば正しいメロディーを導き出せる
- 移調(曲のキーを変えること)に対応しやすい
- 和音やメロディーの構造を理解しやすい
相対音感のデメリット
- 基準音がないと音名を判別しにくい
- 単独の音を聞いただけでは、正確な音程を判断するのが難しい
絶対音感と相対音感は、それぞれ異なる特性を持つ音楽的な能力です。絶対音感は特定の音を瞬時に判断できる能力であり、主に幼少期に習得されます。一方、相対音感は音と音の関係を聞き取る力であり、大人になってからでも訓練次第で身につけることができます。音楽を演奏するうえでは、絶対音感がなくても相対音感を鍛えることで十分に対応できます。どちらの能力も音楽を楽しむための大切な要素ですので、自分に合った方法で音を感じる力を育てていきましょう。
さっそく試そう!絶対音感チェック方法
「自分には絶対音感があるのかな?」と思ったことはありませんか?絶対音感は、基準となる音がなくても単独の音を聞いただけで、その音名(ド・レ・ミなど)を正しく判断できる能力です。ピアノがなくても、スマホや身の回りの音を使って簡単にチェックすることができます。ここでは、絶対音感を確かめるための4つの方法をご紹介します。
ピアノや楽器の音を当ててみる
最も基本的なチェック方法は、ピアノや楽器の音をランダムに鳴らし、それが何の音かを答えてみることです。
- まず、誰かにランダムで鍵盤を押してもらう(スマホのピアノアプリでもOK)。
- 音を聴いて、「これはドかな?」「ソかな?」と答える。
- 答え合わせをして、どれくらい正確に当てられるか確認する。
正解率が高ければ、高いほど絶対音感の可能性があります。ただし、相対音感がある人でも、鍵盤の並びや記憶力を使って当てることができるため、正確な判断には他のチェック方法も試してみましょう。
基準音なしで特定の音を思い出せるか試す
絶対音感を持つ人は、基準となる音がなくても、頭の中で正しい音を思い浮かべることができます。
- まず「ド」や「ラ」など、特定の音を心の中で思い出してみる。
- その音を声に出して歌う。
- ピアノやアプリで正しい音を鳴らし、自分の歌った音と比較する。
誤差がほとんどなく正しい音程を歌える場合は、絶対音感を持っている可能性があります。ただし、訓練で身についた音の記憶による場合もあるので、何度か試してみるとよいでしょう。
日常生活の音が何の音かを意識してみる
絶対音感を持つ人は、音楽の音だけでなく、日常の音に対しても「ド」「ミ」「ソ」などの音名として認識することが多いといわれています。
- 電話のプッシュ音、電子レンジの「ピー」、車のクラクションなどを聞く。
- それが「どの音に聞こえるか」考えてみる。
- ピアノやアプリで確認し、本当に合っているかチェックする。
身の回りの音が自然と音名で聞こえている場合は、絶対音感を持っている可能性が高いでしょう。
和音を聴いて、個々の音を識別できるか試す
単音だけでなく、複数の音が同時に鳴ったときに、それぞれの音名を正しく判別できるかも重要なポイントです。
- ピアノで2つ以上の音を同時に鳴らしてもらう(例:「ド」と「ミ」)。
- それぞれの音を聞き分け、何の音が鳴っているか答える。
- 鳴らした音を確認し、どれくらい正確に判別できたかをチェックする。
絶対音感を持つ人は、和音を聞いたときに「ドとミとソ」と瞬時に識別することができます。一方、相対音感の人は「この和音はCのコードっぽい」と判断する傾向があります。単音は当てられるけど、和音になると難しく感じる場合は、相対音感が強い可能性もあります。


絶対音感を持っているかどうかを確かめるには、楽器の音を当てるだけでなく、基準音なしで音を思い出せるか、日常の音が音名で聞こえるか、和音を識別できるかなど、さまざまな方法でチェックすることが大切です。もし全てのテストで高い正解率を出せたら、あなたには絶対音感の才能があるかもしれません。音楽の世界をもっと楽しむために、ぜひ試してみてください。
絶対音感はどうやって身につくのか?
絶対音感は、生まれつき持っている才能のように思われがちですが、実は適切なトレーニングを行うことで身につけることができるといわれています。特に幼少期に音楽的な環境に触れることが重要で、早い時期から訓練を始めることで、音を聞き分ける力が自然と養われます。ここでは、絶対音感を身につけるための具体的な方法を4つ紹介します。
音の名前を覚えることから始める
絶対音感を習得するためには、まず「音の名前」を正しく認識することが重要です。ピアノや音叉などの楽器を使い、「これはド」「これはミ」と音名を意識しながら聞く練習をします。はじめは単音からスタートし、徐々に複数の音を聞き分けるトレーニングに移行すると効果的です。特に幼少期は、音を言葉として覚えやすい時期なので、日常的に音を聞かせながら「この音は何?」と問いかける習慣をつけると、自然と音名を記憶できるようになります。
日常的に音を聞き、音名を意識する
楽器の音だけでなく、生活の中にある音を意識することも絶対音感を養うトレーニングになります。例えば、電子レンジの「ピー」という音、車のクラクション、風鈴の音などを聞いたときに、「この音はソに近い」「これはレっぽい」と考える習慣をつけることで、音名と音の高さを結びつける力が育ちます。絶対音感を持つ人は、自然と日常の音を「音名」として聞いていることが多いため、この意識を持つことで少しずつ音を識別する力が高まります。
親や先生が音を出し、答える練習をする
幼児が絶対音感を身につけるためには、遊びの中で音を学ぶことが効果的です。親や先生がピアノの鍵盤をランダムに押し、「この音は何かな?」とクイズ形式で問いかけることで、ゲーム感覚で楽しく音を覚えることができます。はじめは「ド」「ソ」など、特徴的な音からスタートし、慣れてきたら半音(黒鍵の音)も含めたトレーニングに移行すると、より正確な音感を身につけることができます。繰り返し行うことで、音を聞いた瞬間に音名を認識する力が鍛えられます。
継続的なトレーニングを行う
絶対音感は、短期間で身につくものではなく、継続的な練習が必要です。毎日少しずつ音を聞き、音名を答えるトレーニングを続けることで、脳が音を記憶しやすくなります。特に3〜6歳の間に音楽に触れる機会を増やし、繰り返し学ぶことが大切です。大人になってからでも、相対音感を鍛えることで音の識別能力を向上させることは可能ですが、完全な絶対音感を身につけるのは難しくなるといわれています。そのため、できるだけ早い段階から音楽に触れる環境を整えることが、習得の大きなカギとなります。


このように、絶対音感を身につけるには、音の名前を覚えること、日常の音に意識を向けること、親や先生と一緒に音を学ぶこと、そして継続的にトレーニングを行うことが重要です。特に幼少期に楽しみながら学ぶことが、自然に音感を育てる大きなポイントになります。
絶対音感があるとどんなメリットがある?
絶対音感を持っていると、音楽の分野だけでなく、日常生活や他の学習にもさまざまなメリットがあります。特に、音楽を演奏する際の利便性が高まり、音楽表現の幅が広がることが大きな特徴です。ここでは、絶対音感を持つことの具体的なメリットを4つ紹介します。
楽譜がなくても耳コピができる
絶対音感があると、音楽を聴いただけで正確に音を捉えることができるため、楽譜がなくても曲を再現できるようになります。たとえば、ピアノやギターで「この曲を弾いてみたい」と思ったときに、CDや動画を聴くだけでメロディーやコードを瞬時に識別し、すぐに演奏できるようになります。これは、楽譜を読むのが苦手な人にとっても大きな強みとなり、自由に音楽を楽しむことができるようになります。


楽器のチューニングが正確にできる
楽器を演奏するとき、正しい音程で演奏することはとても重要です。絶対音感を持っている人は、チューニング(楽器の音を正しい音程に合わせる作業)を耳だけで行うことができます。例えば、ピアノの調律やギターのチューニングをするとき、基準音(A=440Hzなど)がなくても正しい音に合わせることが可能です。これは、オーケストラやバンドで演奏する際にも大きな利点となり、演奏のクオリティを向上させる助けになります。
音楽理論の理解が深まり、作曲や編曲に役立つ
絶対音感を持つことで、音楽を「感覚的」に理解しやすくなり、作曲や編曲の際に大きな助けとなります。たとえば、メロディーやコード進行を頭の中で思い描き、それをそのまま楽器で演奏したり、楽譜に書き起こしたりすることがスムーズにできるようになります。また、和音(コード)の構成音を瞬時に聞き分けることができるため、曲の分析やアレンジがしやすくなります。音楽制作において、より自由に創作活動ができるようになるのは、大きなメリットといえます。
言語学習や集中力向上など、音楽以外の分野でも役立つ
絶対音感を持っている人は、細かい音の違いを聞き分ける能力が高いため、言語の発音やリスニング能力にも優れていることが多いといわれています。特に、英語などの外国語を学ぶ際に、細かいイントネーションや発音の違いを正確に聞き取ることができるため、リスニング能力の向上に役立つとされています。また、音に敏感であることから、集中力が鍛えられ、音楽以外の分野でも高いパフォーマンスを発揮することができる可能性があります。
絶対音感を持っていると、楽譜がなくても耳コピができる、楽器のチューニングが正確にできる、音楽理論の理解が深まる、言語学習や集中力向上に役立つなど、多くのメリットがあります。ただし、絶対音感がなくても、相対音感を鍛えることで十分に音楽を楽しんだり、演奏技術を向上させたりすることは可能です。大切なのは、音楽を楽しみながら、自分に合った方法で音感を伸ばしていくことです。
まとめ
絶対音感は、生まれ持った才能のように思われがちですが、実は簡単な方法で自分にその素質があるかをチェックすることができます。ここでは、今すぐ試せる3つの方法をまとめました。
楽器やスマホアプリで音を当てる
ピアノやスマホの音楽アプリを使い、ランダムに鳴らした音を聞いて、何の音かを当ててみましょう。正解率が高いほど、絶対音感を持っている可能性が高くなります。単音だけでなく、和音(複数の音)も判別できるか試してみると、より正確にチェックできます。
日常の音を音名として聞こえるか試す
絶対音感を持つ人は、楽器の音だけでなく、電子レンジの「ピー」、車のクラクション、ドアのチャイムなどの音も、自然と「ド」「レ」「ミ」のように聞こえることが多いです。普段の生活の中で音を聞いたときに、「この音は何の音に近いかな?」と意識してみると、自分の音感のタイプが分かるかもしれません。
基準音なしで音を再現できるか試す
楽器の音を何も聞かずに、「ド」や「ラ」など、特定の音を頭の中で思い浮かべて、それを口ずさんでみます。その後、ピアノやスマホアプリで正しい音を鳴らし、自分の出した音とどれくらい一致しているかを確認しましょう。もし大きなズレがなく正確に再現できていれば、絶対音感を持っている可能性があります。


絶対音感があるかどうかは、意外と簡単な方法でチェックできます。もし、すべての方法で高い正解率を出せたなら、あなたには絶対音感の素質があるかもしれません。ただし、音楽を楽しむうえで最も大切なのは、絶対音感の有無ではなく、音をよく聴き、感じることです。自分の音の聞こえ方を知りながら、音楽の世界をもっと楽しんでみましょう。