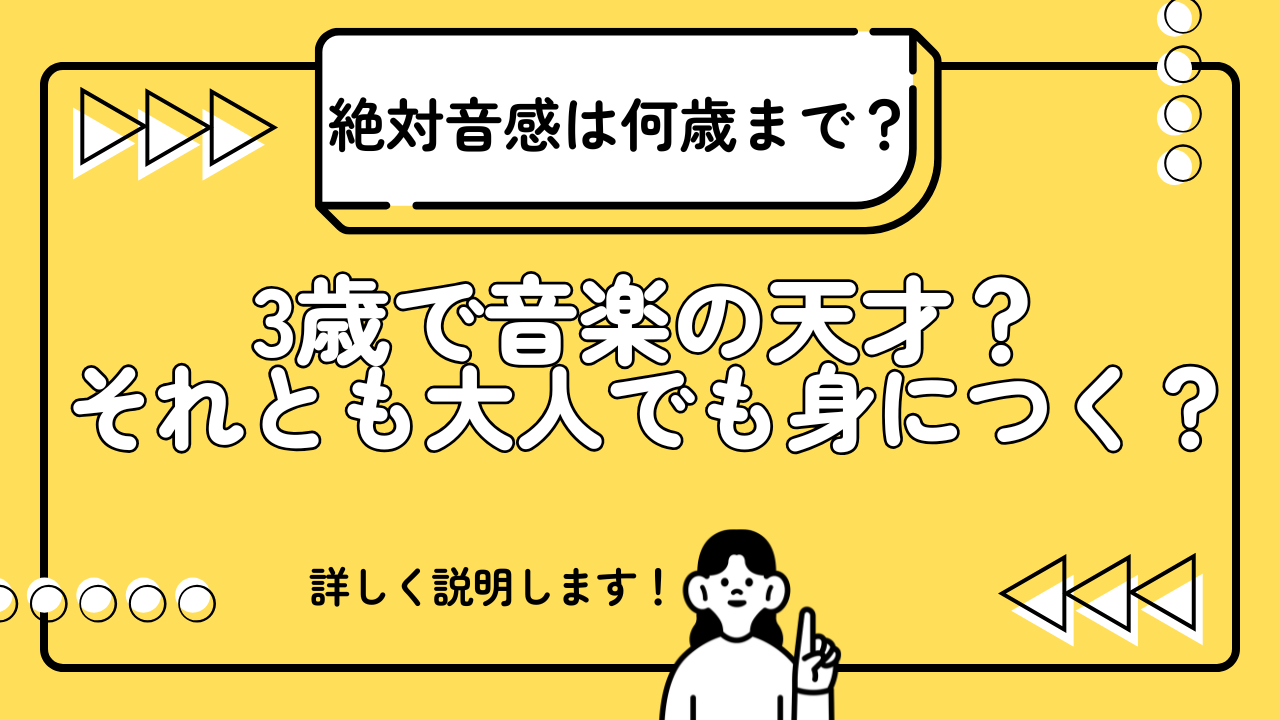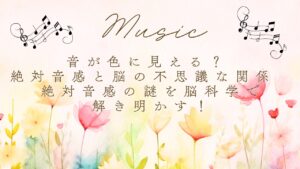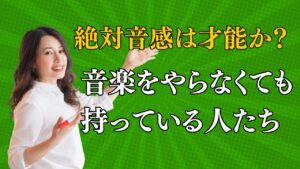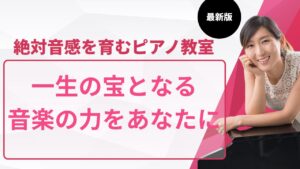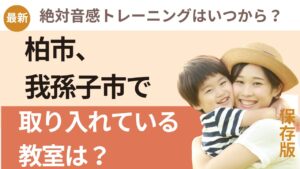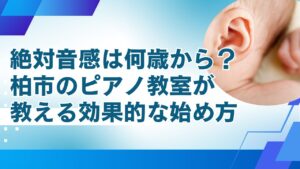「ピアノの音を聞いただけでドレミがわかる」「救急車のサイレンが“シとファ”に聞こえる」――これが噂の絶対音感。テレビやネットで「3歳までに鍛えないとダメ!」という説を聞いたことがある人も多いでしょう。でも、ちょっと待って。本当に3歳を過ぎたら無理なの?大人になってからは絶対に身につかないの?実は、絶対音感の習得には「年齢」だけでは語れない、興味深い秘密が隠されています。今回は、「何歳までなら習得できるのか?」という疑問を掘り下げながら、意外と知られていない絶対音感の面白い話を紹介していきます!
 平田先生
平田先生絶対音感の真実をお話ししますね。
絶対音感は「3歳まで」が本当か? → 実は〇歳でも身につく!?
「絶対音感を身につけるには3歳まで!」という話を聞いたことがある人は多いかもしれません。幼児向けの音楽教育では「今がチャンス!」と強調され、親たちも「この時期を逃したらもう手遅れ!?」と焦ることも。しかし、本当に3歳を過ぎたら絶対に習得できないのでしょうか?実は、「3歳まで」という説には誤解があるのです。年齢による違いはあるものの、大人でも後天的に音感を鍛えられる可能性があることが研究で示されています。ここでは、「絶対音感は何歳まで身につくのか?」という疑問について、意外な視点から解説していきます。
「3歳までが有利」は脳の特性が関係している
「絶対音感は3歳までに鍛えないとダメ!」という説は、脳の発達と関係があります。幼児の脳は非常に柔軟で、言葉を覚えるように音を「名前」として認識する力が強い時期です。このため、小さいうちに音楽に触れ、音を意識する環境があれば、絶対音感を身につけやすくなります。しかし、だからといって「3歳を過ぎたら無理!」というわけではありません。大人の脳は子どもに比べて吸収力が落ちるものの、努力次第で音の識別能力(相対音感)を鍛えることは可能。語学学習と同じで、幼少期に覚えた方がスムーズなだけで、大人になっても練習次第で身につく人はいるのです。つまり、「3歳まで」が有利な時期であることは確かですが、必須条件ではないということです。


7歳までならセーフ!?
「3歳まで」はさすがに短すぎる!と思うかもしれませんが、実は「7歳くらいまでなら絶対音感が身につく可能性が高い」という説もあります。これは、脳の可塑性(柔軟性)がまだ高く、聴覚が発達する時期であるため。実際に、多くの音楽教育機関では「小学校に入るまでがラストチャンス!」と謳っています。しかし、7歳を超えたら本当に無理なのか?というと、これもまた微妙なところ。絶対音感を持つ大人の中には、「8歳以降にピアノを始めて習得した」というケースもありるようです。年齢の影響はあるものの、結局は「どれだけ音に触れ、意識的に訓練したか」がカギなのです
「大人になっても絶対音感を手に入れた人」は実際にいる!
「3歳や7歳を超えたら無理!」と思っていた人にとって驚きの事実ですが、大人になってから絶対音感を手に入れた人も存在します。特に、絶対音感を「相対音感」から逆算して習得したケースがあると報告されています。相対音感とは、「基準となる音」を聞いたうえで、他の音の高さを判断する能力のこと。この相対音感を極限まで鍛え、瞬時に基準音なしで判断できるようになった人は、結果的に絶対音感と同じような能力を手に入れたといいます。これは、「大人になっても耳は成長する」ことを示す興味深い例です。
「絶対音感」は後天的に習得できるが、「自然に身につく」わけではない
では、大人になってから絶対音感を身につけよう!と思った場合、何をすればいいのでしょうか?ここで重要なのは、「自然に身につく」ことはほぼないという点です。幼少期の場合、音楽に触れるだけで自然と絶対音感が育つことがありますが、大人の場合はそうはいきません。後天的に絶対音感を得るには、頻繁に音を聞いて音名を意識する、音感トレーニングを継続する、ある程度の期間、努力を続ける、といった積極的なアプローチが必要になります。例えば、ある研究では「1年間、毎日30分間音感トレーニングをしたグループが、絶対音感に近い能力を得た」という結果が報告されています。つまり、年齢による壁はあっても、しっかりと訓練を続ければ、絶対音感に近いスキルを後天的に身につけることが可能なのです。
「絶対音感は3歳まで!」という説は、あくまで「幼少期の方が習得しやすい」という意味であり、それを過ぎたら完全に不可能というわけではありません。7歳くらいまでなら脳の可塑性が高く、比較的スムーズに習得できる可能性がありますし、大人になってからでも鍛えれば絶対音感に近い能力を手に入れた人もいます。つまり、絶対音感は「天性の才能」ではなく、「音と向き合う時間」と「トレーニング次第」で身につく可能性がある能力」なのです。もし「自分も挑戦してみたい!」と思ったなら、今からでも遅くはないかもしれませんよ。
絶対音感があると「日常生活」がちょっと特殊になる
絶対音感」と聞くと、音楽の才能に恵まれた特別な人たちが持つ能力、というイメージがありますよね。確かに、ピアノを弾くときに「これはド」「これはソ」と瞬時にわかるのは便利そうですが、実は日常生活の中では、思わぬ影響を受けることも多いのです。音楽の世界では役に立つ能力でも、普通の生活の中では「気になりすぎて困る」「周りの人には理解してもらえない」という場面も…。今回は、絶対音感があると日常生活がどんなふうに“特殊”になるのかを、面白いエピソードとともに紹介します!
家の中の「生活音」が、すべて音階に聞こえてしまう
絶対音感を持っている人は、音を「高さ(音階)」として感じるため、普通の生活音まで勝手にドレミに変換されてしまうことがあります。例えば、電子レンジの「ピピピ!」が「ソ・ソ・ド」に聞こえたり、洗濯機の終了音が「ラ・ファ・ド」で頭の中に残ったり。冷蔵庫のブーンという低音まで「これはミの♭だな…」と考えてしまうことも。こうなると、音楽の授業でもないのに家の中が常に「音楽分析の場」になってしまうのです。家族が何も気にせず生活している中、絶対音感を持つ人だけが「この家の家電、全部ヘ長調で鳴ってる…!」と気づいてしまい、1人だけ不思議な世界に生きている感覚になることも。(苦笑)
救急車やインターホンの音が「音楽分析の対象」になってしまう
街で救急車のサイレンが鳴ると、普通の人は「あ、救急車だ」と思うだけ。しかし、絶対音感の持ち主は、「あれはシとファの音程だな…」と冷静に分析してしまうことがあります。また、家のインターホンが鳴ったときも、「誰か来た!」より先に「ド・ソの和音だな」と脳が先に処理してしまい、会話の前に音楽理論が働いてしまう。こうなると、音楽脳が発動しすぎて、普通にリアクションするのが難しくなることもあるのです。さらに、電車の発車メロディーやコンビニの入店音なども気になりすぎて、「この音、よく考えたら途中で転調してる!?」と頭の中でコード分析を始めてしまい、目的を忘れてしばらく音楽考察に没頭してしまうことも…。
カラオケで「キーの違い」が気になりすぎて楽しめない
カラオケで「この曲、ちょっとキー下げよう」と軽く設定を変えることがありますが、これが絶対音感の持ち主にとっては地獄の時間になることがあります。普通の人は「ちょっと低くなったな」くらいにしか感じませんが、絶対音感がある人は「本来の曲はEメジャーなのに、今Gメジャーで歌ってる…頭が混乱する…!」と、原曲とのズレに違和感が止まらないのです。さらに、相手が音程を少し外して歌うと、「あぁ…今のフレーズ、本当はソのはずなのに、ソ♭になってる…!」と、本来なら気にしなくていいズレが気になりすぎて、純粋に楽しめなくなることも。友達が「楽しかったね!」と盛り上がる中、絶対音感の持ち主だけが「気持ち悪い…原曲の音が恋しい…」と頭を抱えることもあるのです。


楽器のチューニングがズレていると、精神的ダメージを受ける(笑)
普通の人は、楽器の音が少しズレていても「まぁこんなもんか」と気にせず演奏できますが、絶対音感のある人はそうはいきません。ピアノの調律が少し狂っていると、「この鍵盤、本当はAなのに、Aの♭にズレてる…!」と一音一音が気になってしまい、演奏よりも音のズレがストレスになることも。また、吹奏楽やオーケストラで演奏する際、他の楽器がほんの少しピッチ(音の高さ)がズレていると、「あああああ!!!気持ち悪い!!!」と心の中で悲鳴を上げながら演奏しなければならない場面もあります。特に、大勢で合わせる合唱やバンドでは、みんなが「まぁいい感じ!」と気にせず進める中、絶対音感の人だけが「いや、音程バラバラすぎるでしょ!」と1人だけ苦しむことになってしまうのです。
絶対音感は、音楽をするうえでは確かに便利な能力ですが、日常生活の中では「気にならなくていい音まで聞こえてしまう」という特殊な体験を生むこともあります。家電の音が勝手にドレミに変換されたり、カラオケで違和感が止まらなかったり、楽器のズレに敏感すぎてストレスを感じたり…。こうした「一般人には分からない絶対音感の世界」は、まるで「音の見える特殊能力」を持っているようなもの。でも、もしあなたに絶対音感がなくても大丈夫。むしろ、「音程のズレが気にならないこと」こそ、ストレスフリーな幸せかもしれませんよ。
絶対音感が「音楽の才能」につながるとは限らない?
「絶対音感がある=音楽の天才」というイメージを持っている人は多いかもしれません。ピアノの鍵盤を適当に押しても瞬時に「これはファ♯!」とわかるし、楽譜がなくても耳コピで演奏できる…確かに、音楽の世界では有利に見えますよね。でも、実は絶対音感があることと、音楽の才能があることはイコールではないのです。「絶対音感があっても作曲は苦手」「リズム感がない」「歌うとズレる」など、音楽の才能とはまったく別の悩みを抱えている人も…。今回は、「絶対音感があるからといって、音楽の才能があるとは限らない」という、意外なギャップについてお話しします。
絶対音感があっても「リズム感」がないと演奏は難しい
絶対音感があると「音の高さ」は正確にわかるけれど、それだけでは音楽を上手に演奏できるとは限りません。音楽には「リズム」が不可欠ですが、絶対音感とリズム感はまったく別の能力だからです。例えば、ピアノの鍵盤を聞いた瞬間に「これはド!」と即答できても、それを正しいテンポで演奏できるかどうかは別の話。リズム感がないと、拍に合わせられず、せっかく音がわかっていても「何かズレてる演奏」になってしまうことも…。
特に、クラシック音楽は楽譜通りに演奏する力が求められますが、ジャズやポップスでは「ノリ」や「グルーヴ感」が大事。絶対音感があっても、それが即興演奏やリズム感の向上につながるわけではないため、「音は正確なのに、演奏がぎこちない…」という状況に陥ることもあります。
作曲しようとしても「音が正確すぎて逆に難しい」
作曲にはメロディーやコードを組み立てる創造力が必要ですが、絶対音感があると「正しい音を聞き分けすぎる」ことで、逆に作曲が難しくなることがあります。
例えば、普通の人は「なんとなくこのメロディー好き!」と感覚で作曲できるのに、絶対音感がある人は「このコード進行、普通はE♭なのに、ここだけC#に聞こえて違和感がある…」と、細かい部分が気になりすぎてしまうのです。さらに、絶対音感を持っていると、「頭の中で音を自由に動かす」よりも「聞こえた音をそのまま再現する」ことに意識が向きやすいため、ゼロからメロディーを生み出すのが苦手な場合も。結果として、「絶対音感があるけど作曲はできない」という矛盾が生まれてしまうのです。
絶対音感があると「音のズレが気になりすぎて、逆に歌えない」
歌が上手な人は、耳の良さと声のコントロール力を兼ね備えていますが、絶対音感を持っているからといって歌が上手くなるわけではありません。むしろ、「音のズレが気になりすぎて歌えない」というケースもあります。例えば、カラオケで自分の声がほんの少しピッチ(音程)がズレただけで、「あっ!今のラの音が微妙にフラット(低め)になった…」と気になってしまい、歌に集中できなくなることがあります。また、周りの人と合唱をするときも、みんながなんとなく合わせて歌っている中で、「あれ?今のパート、微妙に音程ズレてない?」と感じてしまい、逆に気持ちよく歌えないこともあるのです。音の正確さにこだわりすぎて、自由に歌えない…これが絶対音感がある人の、ちょっと意外な悩みかもしれません。
相対音感のほうが「音楽的に便利」な場面が多い
現場では、音楽の流れの中で音程の関係性を捉える「相対音感」のほうが重要になることが多いのです。例えば、ピアノやギターで「キーを変えて弾いてみよう!」という場面では、絶対音感の持ち主は「今までCメジャーだったのに、いきなりEメジャーに転調すると頭が混乱する…」と、音の変化についていけなくなることがあります。一方、相対音感の人は「音の高さよりも、メロディーの流れやコードの関係性を重視」するため、転調や即興演奏がスムーズにできます。音楽の現場では、絶対音感がなくても相対音感がしっかりしていれば、柔軟に対応できることが多いのです。つまり、「絶対音感がなくても、音楽的なセンスは十分磨けるし、むしろ相対音感のほうが演奏には便利」ということになります。


「絶対音感がある=音楽の才能がある」というのは、一見もっともらしいですが、実際にはそうとも限りません。リズム感がないと演奏は難しいし、作曲では音が正確すぎて逆に自由に考えられなくなることも。さらに、歌うときに音のズレが気になりすぎて逆に歌えなくなったり、即興演奏では絶対音感よりも相対音感のほうが役に立つ場面が多かったりします。つまり、絶対音感はあくまで「音を聞き取る能力」であって、それが音楽の才能につながるかどうかは別問題。音楽を楽しむために必要なのは、音の高さだけではなく、リズム、表現力、柔軟な感性も含めた総合的なスキルなのです。
実は「邪魔になる」ことも!? 絶対音感の意外なデメリット
「絶対音感」と聞くと、音楽の世界では“最強の才能”のように思えます。音を聞くだけでドレミがわかる、楽譜がなくても耳コピできる、楽器の音を完璧に識別できる…確かに便利そうですよね。でも、実は**「絶対音感があるせいで困ること」**も意外と多いのです。例えば、カラオケでキーを変えられると頭が混乱する、周囲の音のズレが気になりすぎてイライラする、楽器の調律が少し狂っていると演奏どころではなくなる…。こうした“意外なデメリット”に苦しむ絶対音感の持ち主は少なくありません。今回は、「絶対音感があるがゆえに邪魔になること」を、4つの面白いエピソードとともに紹介します!
カラオケでキー変更が「地獄」になる
カラオケでは、「ちょっとキーを下げて歌おう!」ということがよくありますよね。でも、絶対音感の持ち主にとってはこれが耐えがたい苦痛になることがあります。
普通の人は「少し低くなったな」くらいの感覚で済みますが、絶対音感の人は「原曲はBメジャーなのに、今Aメジャーで流れてる…音の高さが全部違う…」と混乱してしまうのです。結果、「歌うどころじゃない!違和感がすごすぎる!」と、頭の中がパニック状態に。さらに、友達が音程を外して歌うと、「あぁ…本当はソのはずなのに、ソ♭になってる…」と耳が正確すぎるがゆえに気になってしまい、純粋に楽しむことができないことも。カラオケが「音楽を楽しむ場」ではなく、「音程の狂いに耐える修行の場」になってしまうのです。
楽器のチューニングが少しでもズレていると精神的ダメージを受ける
絶対音感があると、楽器の音がほんの少しでもズレているとすぐにわかります。ピアノの調律が狂っていたり、ギターのチューニングが少し低かったりすると、もうそれだけで気になって演奏に集中できないのです。普通の人なら「ちょっとズレてるかも?」くらいで済むのですが、絶対音感の人は「このピアノ、Aの音が少しフラットになってる…」と、一音一音が引っかかってしまい、まともに演奏できなくなることも。さらに、オーケストラや吹奏楽で他の楽器の音が微妙にズレていると、「ああああ!全員、チューニング直してくれ!!!」と心の中で叫びたくなるほどストレスを感じることもあります。音に敏感すぎるせいで、演奏を楽しむどころか、「音のズレとの戦い」に突入してしまうのです。
日常生活の「どうでもいい音」までドレミに聞こえてしまう
絶対音感の持ち主は、音楽の世界だけでなく、日常生活のあらゆる音までドレミに聞こえてしまうという“困った現象”に悩まされることがあります。例えば、電子レンジの「ピピピ!」が「ソ・ソ・ド」に聞こえたり、救急車のサイレンを聞くと「シとファの音程だな…」と分析してしまったり。さらに、電車の発車メロディーが「転調してるな」と気になったり、エアコンのブーンという音が「これはG♯の音だ」と頭の中に残ったり…。これが何を意味するかというと、「集中すべき場面でも余計な音が気になりすぎる」こと。授業中や仕事中でも、ふとした瞬間に周囲の音を分析し始めてしまい、「あのキーボードのタイピング音、全部B♭だな…」と余計な情報が脳に入ってきてしまうのです。
音楽の才能どころか、むしろ「雑音のせいで集中できない」という状況になり、日常生活にちょっとした支障をきたしてしまうことも。
外国語の発音が難しくなることもある!?
絶対音感があると、言語の音の微妙な違いに敏感すぎて、外国語の発音をうまく真似できないことがあると言われています。例えば、日本語にはない「R」と「L」の違いを聞き分けるのは絶対音感の人にとって簡単ですが、逆にその正確さが仇となり、「ネイティブの発音を微妙に間違えているのが気になりすぎて、自分で発音するのが難しくなる」ということが起こるのです。また、英語のイントネーションやアクセントが「音楽のメロディーのように」聞こえてしまい、「この単語のイントネーション、GからAに上がる感じで発音しなきゃ…」と余計な意識が働き、かえって自然な発音ができなくなることもあるそうです。つまり、絶対音感があることで、「聞き分ける力」は高まるものの、「実際に発音する力」が逆に難しくなるという、不思議なジレンマに陥ることがあるようです。


絶対音感は音楽の世界では確かに便利な能力ですが、日常生活では「音が正確すぎるがゆえに困ること」が意外と多いものです。カラオケではキー変更がつらく、楽器のチューニングがズレると精神的ダメージを受け、どうでもいい生活音までドレミに聞こえてしまう…。さらに、言語の発音にも影響が出ることまであるとは驚きですよね。「絶対音感があったら音楽がもっと楽しめるのに!」と思っていた人も、これを読んで「むしろない方が幸せかも…」と感じたかもしれません。結局のところ、音楽は「楽しむこと」が大切。絶対音感があるかどうかに関わらず、心から音楽を楽しめる耳を持つことが、一番の才能なのかもしれませんね!。
まとめ
絶対音感と聞くと、「3歳までに鍛えないとダメ!」「音楽の天才になれる能力」といったイメージを持たれがちですが、実際にはそれほど単純な話ではありません。年齢に関係なく習得の可能性はあり、持っていることでのメリットもあれば、意外なデメリットもあるのが面白いところです。では、絶対音感について押さえておきたいポイントを3つにまとめてみましょう。
絶対音感は幼少期が有利だが、音感は大人でも鍛えられる
3歳までが習得しやすいと言われるのは脳の柔軟性の影響。でも、努力次第で大人でも後天的に身につけることは可能。音楽に興味があれば、年齢を気にせずトレーニングしてみる価値はある。
絶対音感=音楽の才能ではない
音を瞬時に識別できることと、音楽が上手いことは別の話。絶対音感がなくても、相対音感を鍛えれば素晴らしい音楽表現ができる。むしろ、音楽を楽しむうえでは、柔軟な耳の方が役立つことも。


絶対音感が邪魔になる場面もある
音に敏感すぎることで、カラオケや調律のズレが気になったり、日常のさまざまな音がストレスになることも。便利な能力だけど、一長一短な側面もある。
絶対音感は「特別な才能」というよりも、「持っているとちょっと世界の聞こえ方が変わる面白い能力」。あるに越したことはないけれど、なくても音楽を楽しむことは十分可能です。大事なのは、音を楽しむ気持ち。あなたの耳も、今からでももっと鍛えられるかもしれませんよ。